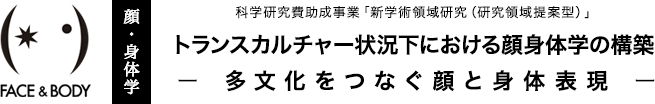研究組織
公募研究
A01-K201 | お辞儀が印象形成に及ぼす影響の文化間比較
大杉 尚之 (山形大学人文社会科学部)
詳細を見る日本において、「お辞儀」が第一印象に影響することは、学校教育や入社後の新人研修セミナーで特集を組まれるなど一般的に信じられている。しかし、お辞儀に関する実験的研究はほとんど行われてこなかった。申請者らは、日本人の大学生を対象とした実験を行い、お辞儀が顔の魅力を上昇させることを明らかにした。その原因について日本の文化的背景の影響を仮定してきたが、日本人だけを対象とした実験では結論づけることはできない。そこで本研究では、複数の文化圏の集団に対してお辞儀が人物印象に及ぼす影響を検討し、この効果の文化依存性を明らかにすることを目的とする。
研究1では西洋と東洋の集団に対して、お辞儀が人物印象に及ぼす影響を検討する。コンピュータグラフィック(CG)の人物モデルにお辞儀をさせ、動作後にその人物の印象(魅力、礼儀正 しさ、従順さ)を評定する実験を行う。この条件と静止したままの条件を比較し、お辞儀により印象が良くなるかを検討する。また、お辞儀動作の3つのフェイズ(屈曲、停止、伸長)モデルの人種を操作し、文化的背景が及ぼす影響について検討する。研究2では、東洋の文化圏内における比較から、お辞儀の日常的な習慣が及ぼす影響を検討する。社会的文脈(挨拶場面、謝罪場面、お礼場面)ごとの適切なお辞儀の深さ、長さも合わせて調べる。お辞儀の機能や日常的習慣の違いにより、お辞
儀の効果量がどのように変化するかを明らかにする。研究3では、お辞儀の習慣がない文化圏も含めて比較をすることで、お辞儀動作の文化普遍的な意味づけについて検討する。 頭を下げるという姿勢は相手への服従の意味も持つことから、お辞儀をする人物に対して東洋とは異なった解釈がなされる可能性がある。以上のように多層的な比較により、お辞儀動作が持つ機能の文化依存性、普遍性を明らかにする。
A01-K202 | 現代マサイ社会における身体表現と認識:相互行為の場に着目して
田 暁潔 (筑波大学体育系)
詳細を見る感情を表す表情や身ぶり、姿勢などの身体表現は、円滑なコミュニケーションの成立に重要な役割をもっている。そのような身体を用いたコミュニケーションは、通信技術の発展によって時間・空間的な制限を超えた新たな交流様式にも存在しており、トランスカルチャー時代におけるコミュニケーションを理解するために、身体表現が重要な手がかりになっている。
本研究は、東アフリカの牧畜民マサイに着目して、トランスカルチャー的な状況におけるマサイと文化的他者との交流の場で、行為者たちがいかに身体を表現・認識し、多様な状況でのコミュニケーションを成り立たせるのかを明らかにする。具体的には、マサイの伝統スポーツを利用した「マサイ・オリンピック」を対象とする。
ケニアでは、マサイのライオン狩りを消滅させるために、2012年から2年ごとに「マサイ・オリンピック」を開催するようになった。これにはマサイのほか、国内外の観光客やスポーツ選手、野生動物保全とかかわる活動家、研究者など、マサイにとっての文化的他者が多数集まる。このイベントにおけるコミュニケーションと身体表現を理解するために、まず、マサイ・オリンピックの開催前後に、このイベントがいかに報道され、マサイの身体的なイメージがどのように描かれてきたのかを既存の研究や新聞記事などから収集・整理する。次に、参加者の文化的・社会的な背景、個人の生活史を理解するための聞き取り調査を実施する。さらに、イベントの当日に各場面におけるコミュニケーションを、言語的・非言語的の両側面から記述・分析する。最後に、以上の3つのステップで収集できたデータを包括的に考察し、トランスカルチャー的な状況におけるマサイの身体表現の特徴と役割を明らかにする。
A01-K203 | フィールド-ラボ循環型アプローチによる身体化された感性の研究
山田 祐樹 (九州大学 基幹教育院)
詳細を見る我々は,これまでに中国雲南省のハニ族・タイ族に対して身体化された感情について研究を行い,独特な文化的影響を炙り出してきた。一連の研究により構築された研究基盤を素地とし,本研究ではテーマを感情から感性に拡張して研究をすすめる。ここで言う感性とは,「アイステーシス (包括的,直感的に行なわれる心的活動およびその能力)」に基づくものであり (三浦,2013),それは美学,感情,認知,知覚など様々をその範囲に含む。したがって,感性を理解するためには,多方面からのアプローチが必要である (遊撃的研究:山田,2018)。
感性は,不定形であり身を置く環境や文化的なバックグラウンドに応じて,ダイナミックに変動する。一方で,感性研究は主に文明化された文化圏に属する人々を対象にし,日常的な環境下で得られたデータを基にした議論に終始している。つまり,非日常的な環境や少数民族が有するような独特な文化的背景を扱った研究はほとんど存在していない。感性を真に理解するには,こうした特殊な環境や文化的背景がもたらす影響を明らかにする必要がある。本研究では,国内の特殊エリア (e.g., 神社仏閣や心霊スポット) や中国の少数民族 (ハニ族・タイ族だけではなく,ミャオ族やチワン族などにも拡張する) の集落を対象としたフィールドワークと,そこで見出された要因を制御した実験室研究を同時並行・相互作用的に遂行し (フィールド-ラボ循環型アプローチ),身体化された感性の機序を明らかにすることを目指す。
フィールドワークでは,集落で生活する人々や神社仏閣の内部者などを対象に半構造化フォーカスグループインタビューによる質的調査とラップトップやタブレット端末を用いた認知実験を組み合わせた混合研究法を用いる。さらに,温度や湿度などの環境計測も行う。一方で,実験室では主にフィールドワークで推定された諸要因を制御し,仮説検証的な研究を行う。
A01-K204 | イレズミ・タトゥーにおけるトランスカルチャー性の比較研究
山本 芳美 (都留文科大学文学部比較文化学科)
詳細を見る本研究は、研究代表者の山本芳美(都留文科大学)と研究協力者の山越英嗣(早稲田大学人間科学学術院・助教)、秦玲子(日本文化人類学会・会員)が、これまでフィールドワークをしてきた沖縄や地域と民族について、イレズミ・タトゥーをめぐる人々のトランスカルチャー的実践の研究をおこなうものである。
本研究班は、2018 年に「顔・身体学」の公募班に採用された「トランスカルチャー状況下における顔身体学の構築―多文化をつなぐ顔と身体表現」の後継プロジェクトであり、さらに深化、発展させることを目指す。彫師とその客、ならびに客同士、彫師や彫師同士の交流、さらに他の領域に広がる交流や拒絶、断絶に着目し、その歴史的変遷や影響のあり方を解き明かす。研究代表者と研究協力者がこれまでフィールドワークをしてきた地域について、人々の実践に着目した研究をおこなう。COVID-19により、国内外の移動・調査が難しくなっているため、柔軟に研究を見直す。
2020年度は、①沖縄本島中部でのタトゥーショップ調査と現代ハジチ女性調査、②ニュージーランド、マオリ民族のタ・モコについての調査、③2019 年度 企画展「沖縄のハジチ、台湾原住民族のタトゥー 歴史と今」展にて新たに判明した施術事例の追跡調査と巡回展実施に伴う調査 、④温泉タトゥー問題の実態調査、⑤明治期の日本人彫師の下絵データベース構築を構想している。
現状はフィールドワークが難しいため、まずは⑤を先行させる。国内の複数の所蔵機関で保管されている日本人彫師の下絵に着目して、データベース化を目指して情報の整理、分析に取りかかる予定である。日本人彫師のものと確認されている下絵は、国内外で6か所の所蔵先にあるのみである。下絵は19世紀後半から20世紀初頭の欧米を中心とした客と日本の彫師の交流の集積であるが、消耗品とされてこれまで収集や研究の対象とはなってこなかった。文化人類学者のチームとしては手足を縛られた状況であるが、まずは「STAY HOME」でできる研究に着手するものである。
B01-K201 | 衛生マスクが生み出すポジティブ・ネガティブな顔遮蔽効果
河原 純一郎 (北海道大学 大学院文学院 心理学研究室)
詳細を見る本研究は、衛生マスク(以下マスクと略す)の着用が対人認知に及ぼすポジティブ・ネガティブな影響を調べることを目的とする。世界的には健康な者のマスク装着はインフルエンザ感染予防効果なしとされているにもかかわらず、この度の疫病を契機としてマスクを常時装着のまま他人に接する機会が激増した。マスクの常時着用傾向は、わが国発祥であるとも言える。世界的には少数派であるマスクの常時装着が、対人認知に及ぼす影響と、その背景にある仕組みはほとんど不明のままである。本研究グループでは、遮蔽と不健康さの知覚がマスクを装着した顔の認知に影響することを世界で初めて特定した。国内では、マスクの装着は知覚される不健康さを増すという点でネガティブな効果があることが見込まれるが、もともとマスクの文化がない国や地域での対人認知のバイアスは未知である。増大する外国人の流入の中で、マスク装着が及ぼすインパクトは知っておく必要がある。そこで、マスク装着効果の国際比較を行うことを第1の目的とする。一方、マスク装着の効果はポジティブな側面もありうる。本研究は、マスク装着効果の測定手法(Miyazaki & Kawahara, 2016)や態度推定手法(伊藤・河原, 2019)を拡張し、装着者の対人認知属性を測定することが第2の目的である。特に、日本国内の異世代間認知、社会的文脈の効果を測定する。申請者はパイロット研究を行い、マスクを装着することで不安を低減する可能性があること、加えて初対面の人物に対して自己開示意図が増えることがわかった。そのため、第3の目的としてマスク顔の認知という受動的な側面だけでなく、マスクを装着することによる対人行動の促進や、対人場面での困難の緩和という能動的な側面の両面を扱う(これらは申請当時の案)。本研究は、顔を隠すというマスクのネガティブ面の許容度を国内・世代間・国際間で測定するだけではない。マスクは本来、護る機能をもつ。そのため、マスクのもつ能動的な対人相互作用にポジティブな効果を引き出すことができれば、ストレスケアや対人不安といった領域にも日本発・世界初の突破口を開くことができる。
B01-K202 | コミュニケーション基盤としての顔-身体コーディネーション
工藤 和俊 (東京大学大大学院情報学環・学際情報学府)
詳細を見る近年、ヒトにおける社会的行動の進化的起源として、対人間協調(コーディネーション)の役割が注目されている。ヒトを含む動物の協調に共通する特徴として、1)身体部位間の協調(体肢間協調)、2)外部環境からの感覚情報に合わせた運動の協調(感覚運動協調)、および 3)個体間の協調という重層性が存在することが挙げられる。これら複数の階層にわたる協調行動に通底する組織化原理を記述するための数理科学的方法論として力学系アプローチがある。また近年、動画認識技術が急速に発展し、撮影された動画から身体特徴点(顔や関節中心など)の座標を自動的に抽出することが可能になっている。これら数理解析手法および工学的技術を用いることにより、異なる階層にわたる協調性の定量化および映像データからの協調行動抽出が可能になる。そこで本研究は、他者を含む環境と相互作用するヒトの協調行動に着目し、機械学習技術を利用した身体部位認識および非線形力学系解析を用いたマルチモーダルな協調行動の定量的評価を行うことにより、対人間コミュニケーションにおける身体運動協調の役割を明らかにする。この際、立位や歩行などヒトの基本的運動における対人間協調ダイナミクスを明らかにするとともに、協調行動の発達的側面について検討するため、乳児を対象とした観察研究を実施する。本研究では特に、協力行動など向社会的コミュニケーション行動の発現に至るプロセスにおいて、体肢間、感覚運動、対人間の重層的協調行動に潜むダイナミクスの定量化を試み、これらが互いにいかなる関連のもとで発達するのか検討する。また、協調行動の熟達化について検討するため、即興演劇俳優の演技に着目し、視線、表情、姿勢、呼吸等を含めた身体運動協調の個体内および個体間ダイナミクスの熟達差を明らかにする。これらの研究を通じて、身体の協調(コーディネーション)がコミュニケーションに果たす役割を明らかにする。
B01-K203 | 身体表現における複層的な演者間インタラクションの定量的検討
清水 大地 (東京大学大学院教育学研究科)
詳細を見る身体表現芸術において複数名の演者は、複雑な関わり合いを営みつつ興味深いパフォーマンスを披露する。この演者間の関わり合いは、表現の魅力を形成する重要な要素である。
またこの関わり合いが関係性の強化や共同体の維持・発展に貢献したため、身体表現芸術が社会・文化に広く普及したとする社会的起源も主張されている。実際に、国内外の教育においても、ハーバード大学のリベラル・アーツ教育等で協調・共感能力の育成を目的として身体表現科目を取り入れる試みが営まれている。しかし、この演者間の関わり合いがいかに営まれるのか、その様相に関する定量的検討は十分には行われていない。近年、同期・協調の理論を適用した検討が営まれているが、ピアニストの腕の運動、ダンサーの頭部の運動といった単一の表現媒体(チャンネル)に着目した検討が中心である。一方で身体表現では、表情・ジェスチャー・リズム運動等の複数媒体を通して他演者との複雑な関わり合いが営まれると予想される。そこで本研究では、上記した複数の表現媒体における演者間協調の様相を定量的に検討する。具体的には、1:複数の表現媒体における演者間協調の有無・程度、2:各媒体における演者間協調の様相の共通性・差異、3:各媒体の協調間における高次な対応関係の有無・程度、の3点を検証する。その際、モーションキャプチャーシステムを用いて測定したリズム運動や空間内の移動等の媒体について、同期・協調の理論において適用されてきた線形・非線形の時系列解析(位相解析や交差再帰定量化解析)を適用し、演者間協調の様相を定量的に検討する。なお本研究では、世界中で広く親しまれ、複数名による即興的な表現の披露が文化的に強く根づいているストリートダンスを対象とした。本研究により、複数の表現媒体の関連の重要性やその定量的検討手法が示唆・確立され、多様な身体表現芸術における演者間の関わり合いを捉える基本的な枠組みが構築可能と考えている。以上を用いた関わり合いの領域間比較や文化間比較、熟達度による差異の検討は、トランスカルチャー状況下での顔身体学の発展に大きく貢献できるであろう。
B01-K204 | 脳内電極脳波による顔・身体学と情動・社会性の研究
飯高 哲也 (名古屋大学 脳とこころの研究センター)
詳細を見るヒトの高次脳機能は情動や社会性を含む広範な概念であり、その障害は自閉スペクトラム症など精神疾患の病態にも関与している。情動や社会性の脳機能はヒトが単に生存するだけではなく、文化や生活に必要なこころの働きである。われわれは顔(表情筋)や身体(姿勢・身振り)に表出する様々な感情を認識し、日常的な行動に反映させていく必要がある。本研究では表情認知とその模倣、および姿勢・身振りの認知とその模倣などについて、ヒトを対象とした脳科学的実験を行う。そのために難治性てんかん患者の脳外科手術前に、脳内に埋め込んだ電極を用いて海馬・扁桃体領域から神経活動を計測する。この電極から顔・身体にかかわる心理課題を遂行中のヒトの脳活動を、ミリ秒単位で計測することができる。てんかん患者の脳内電極脳波実験に加えて、健常者を対象とした非侵襲的脳機能計測(fMRI)も行う。fMRIの心理課題は脳内電極脳波実験と同等の内容とし、海馬と扁桃体を中心とした領域の脳活動を調べる。これら2種類の実験結果を統合的に解析し、顔・身体反応のヒトにおける神経基盤を解明する。研究成果としては顔認知や身体模倣など社会性に関わる脳内機構が明らかになることに加え、精神疾患により起きる症状の理解と発症機構の解明につながると考えられる。
研究者ホームページ https://neuroimage.wordpress.com/
B01-K205 | 複数人場面における関係性の認知:発達と文化特異的な認識の発生
上田 祥行 (京都大学 こころの未来研究センター)
詳細を見る私たちは常に多くの他者と交流を持って生活している。円滑な社会生活のためには、相手の性格特性や意図を推測し、それに応じた行動を取らなければならない。これらの推測の中で重要なものの一つは、社会的な関係性の認知である。グループの中でドミナントな人物は影響力も大きく、グループの意思決定で大きな役割を担っている。表出される表情と人物特性の関係を調べたところ、ある人物が「ドミナントな行動を取りやすい」と判断されるかどうかと「ドミナントな立場である」と判断されるかどうかには、異なる判断基準があることがわかった。さらに、このような関係性の認知には文化普遍的な側面(どの文化でも、怒り表情の人物はドミナントな行動を取りやすいと判断されるが、関係性を支配していると判断されるのは笑顔や真顔の人物であるということ)と文化特異的な側面(笑顔や真顔の人物が集団の中でどの程度ドミナントな立場であると判断されるのかは文化によって異なる)があることが示された。関係性認知のメカニズムの水平方向の分散(文化差)が明らかになる一方で、垂直方向の分散(発達段階)は未だ不明である。いくつかの研究では、児童期に文化特異的なモノの見方が育つという報告がある。そこで本研究では児童を対象に、表情による文化特異的な社会的関係性の認知の発達を検討する。また、これまでの研究では二者場面における関係性の認知を対象としてきたが、現実場面により近い、多くの人がインタラクションする状況における集団内関係性の認知についても明らかにすることを目指す。より具体的には、①どの発達段階から、2つの基準を区別し、文化特異的な関係性の認知を獲得するようになるのか、②関係性認知のメカニズムは、より多くの人物が関与している状況でも同様に機能し、文化特異的な差異を産み出すのか、の2点を検討する。
B01-K206 | 大脳皮質と皮質下における顔表情処理の比較:文化間の差異と普遍性に注目して
稲垣 未来男 (大阪大学 大学院生命機能研究科)
詳細を見る顔表情コミュニケーションには文化的な差異と普遍性の両方が存在する。本研究は、表情の種類や特徴に関する文化的な差異ならびに普遍性に対して、大脳皮質処理と皮質下処理がどのように影響するかの解明を目標とする。霊長類で特に発達した大脳皮質処理は、生まれた直後には未熟であり成長とともに周囲の環境を学習して高度に成熟する。一方、進化的に古い皮質下処理は大雑把ではあるが生まれた直後から機能している。大脳皮質処理と皮質下処理は異なる発達経過をたどることから、文化的な差異や普遍性の獲得に異なる貢献をする可能性がある。しかし、その解明には同時に並列的に働く2つの脳内処理の影響を切り分ける必要がある。そこで2つの脳内処理を独立した計算モデルとして構築することで別々に解析・比較する研究を実施する。
これまで前期公募研究において、神経解剖学と神経生理学の知見をもとに大脳皮質処理と皮質下処理を計算モデル化して、2つの脳内処理の特性を調べてきた。特に大脳皮質処理は処理層の多い深層型ニューラルネットワーク、皮質下処理は処理層の少ない浅層型ニューラルネットワークとしてモデル化した。今回の公募研究では計算モデルを使った研究をさらに発展させて、文化的な差異と普遍性に与える影響の解明を目指す。日本やヨーロッパなどの異なる文化圏の表情画像データベースを計算モデルの学習に用いることで、各文化圏特有の表情特徴を計算モデル内に獲得させる。さらにモデル内に学習された特徴を可視化する手法により各文化圏特有の表情特徴を明らかにするとともに、大脳皮質モデルと皮質下モデルが獲得する表情特徴を比較する。学習後に別の文化圏の表情画像データベースをモデルへ入力した場合の汎化性能から、異なる文化圏における表情特徴の類似性も検討する。
B01-K207 | 顎骨形成術後の顔面頭頚部の知覚・運動と自己身体認知との間の因果関係
社 浩太郎 (大阪大学大学院・歯学研究科)
詳細を見るヒトは主として顔面頭頸部の運動を通じて自己表現する。顔面頭頸部に可視的変形(VD)を有する患者は表情表出・咀嚼・構音運動といった運動機能が低い。患者に顎骨形成術を施すことによってそれらの機能が改善する。では新しい自己身体認知は脳内表象の変化や、運動の回復・改善と如何に関連するのだろうか?術後の障害と回復及び機能改善を明確に示すのは、顔面表面の知覚麻痺・運動障害の出現と回復及び運動の改善である。我々の先行研究によると、術後約2年までに顎顔面の知覚や運動が回復し、咀嚼や表情表出の運動円滑性は対照群以上にまで改善する例も多い。また、術後約650日までに新たな自己顔への感度が強まり、対照群よりも強くなることが示された。また術後群では術前群と比べて、視床枕と内側前頭回の活動が大きかった
。回復した自己顔に対する認知の感度が如何なる理由で約2年という長いプロセスで強くなるのだろうか?外科的侵襲後に顔面頭頸部を自己身体として再認知する機構は、知覚・運動の回復に応じて更新され、後に運動機能の改善に寄与するのではないだろうか?実験群を縦断的にサンプリングし、顔面頭頸部の(1)触覚と運動の障害から回復、(2)自己顔・身体の認知とその脳内表現、を定量化して両者の相関を検証すれば、術後の顔面頭頸部の知覚・運動と自己身体認知との間の因果関係を解明できる。本研究では、「自己身体像と運動主体感から見た顔面頭頸部の自己身体認知は、術後の顔面の触覚・運動障害の回復に応じて更新された後に運動機能改善の基盤となる」という仮説を検証するために顎骨形成術前後の顔面の触覚麻痺と回復、運動円滑性の低下から改善までを定量化する。また、 顔面頭頚部の自己身体認知の強さを身体像の精度と運動主体感の強さから定量化する。加えて、(3)自己顔成分の割合を視覚刺激強度とした時の脳機能画像による関心領域の脳活動を神経科学的変量とする。
B01-K208 | 深層学習を用いた身体表現文化差の検討
内藤 智之 (大阪大学大学院 医学系研究科 認知行動科学教室)
詳細を見るヒトはヒトの顔や身体表現に強い魅力を感じる。顔の魅力は、人類に共通の普遍的成分と個人ごとに異なる独自成分によって形成されていることが報告されている。顔の魅力に関する普遍的特徴については多くの研究が報告されているが、個人ごとの独自成分に関する知見は十分であるとは言い難い。これは顔や身体表現を特徴づける画像特徴が非常に高い次元で表現されるため、網羅的に画像特徴を検証することが困難であることが一因である。また顔魅力に関して、ヒトは理想的な魅力顔を心的画像(心的テンプレート)として保持していることが報告されている。この魅力顔心的テンプレートは逆相関法を用いて、画像とし て可視化可能であることも報告されている。しかしこの手法を用いた魅力顔特徴の個人差を定量的に解析することは困難であるという問題あった。以上の問題を解決し、顔魅力の個人ごとの独自成分あるいは文化毎の独自成分を定量化するために深層学習と心理物理学実験を組み合わせたアプローチで以下の研究を推進する。1)深層学習の1つである敵対的生成ネットワーク (GAN) を用いて、顔の画像特徴を512次元ベクトルとして抽出する。3)被験者毎に顔画像魅力度評定課題のスコアを重みとした逆相関法を用いることで、個人が持つ魅力顔心的テンプレートに対応した特徴ベクトルを算出する。3)GANの生成器に2)で算出した特徴ベクトルを入力することで、個人の魅力顔心的テンプレートを高精度自然画像として生成する。4)生成された画像を含む顔画像魅力度評定課題を再度行うことで、生成された顔画像が個人にとって高い魅力度を持つ顔であることを確認する。本研究により顔画像を特徴ベクトルとして定量的に扱えるようになるため、個人間、文化間の魅力顔の違いを特徴ベクトルの距離で定義できるという利点がある。そのため、これまで定性的にしか扱うことのできなかった顔魅力度判断における個人的要因と文化的要因の差や、個人間、文化間の魅力顔の違いを定量的に評価可能となることが期待される。
B01-K209 | 対人インタラクションにおける脳・身体同期への文化差の影響
大須 理英子 (早稲田大学人間科学学術院)
詳細を見る対人インタラクションの場面において、脳活動が同期したり、身体が協調的に動いたりすることが知られている。また、そのような同期協調ダイナミクスの程度は、インタラクションする二者間の社会的関係にも影響を受けることがわかってきた。では、このような脳-身体の同期協調ダイナミクスに、文化や文化差はどのような影響をもたらすのであろうか。心理的・社会的な文化差や、身体表現・身体コミュニケーションの文化差の影響を受けるであろうか。それとも、異文化の人どうしが向き合ったときに、文化の壁を越えた同期や協調が観察されるのであろうか。また、そもそも、対人インタラクションにおける同期協調ダイナミクスの様相に文化差が存在するのだろうか。
これらの疑問に答えるため、本研究提案では、対人インタラクション課題における脳活動および身体の同期協調ダイナミクスについて、同文化間のペアと異文化間のペアで比較することを目指す。それにより、無意識的な社会的相互作用に及ぼす文化的影響を考察する。これらの結果は、「身体的文化性」の近さを反映しうるかもしれない。神経科学において、対人文化差を導入するのは新しい試みであり、文化差の神経表現は、トランスカルチャー状況下において、文化的アイデンティティーを確認する一つの手段となる可能性がある。
なお、異文化条件での実験にあたっては、フィールドに強い計測システムの構築が必要であり、本研究課題での研究項目の一つとしている。脳活動の同期については、環境アーチファクトに脆弱な脳波ではなく、アーチファクトに比較的強い機能的近赤外分光計測装置(fNIRS)を使用する予定である。また、身体協調ダイナミクスの解析には通常フォースプレートと三次元位置計測装置を使用するが、可搬性がないため、加速度計とビデオ画像のAI解析による手法の開発を試みる。
B01-K210 | 相互注視の回避に関わる生理心理学的メカニズムの解明
磯村 朋子 (名古屋大学情報学研究科)
詳細を見るコミュニケーション中の二者が相互に相手の顔を見合っている状態(相互注視)は決して持続的ではなく、1回の相互注視の持続時間は1.5~3.6秒と意外に短いことが報告されている。つまり、私たちはコミュニケーション時に相手の顔を見たり視線を逸らしたりする行動を交互に、短い持続時間で頻繁に生起させているようだ。顔や目は相手の感情や意図を理解するのに最も有用な情報源であるにも関わらず、なぜ私たちはコミュニケーション時に相手の顔や目を継続して見続けないのだろうか。
本研究では、対人コミュニケーション時に頻繁に生起する無意識的な「相互注視の回避」(視線逸らし)には、持続的な相互注視に伴う身体の過度な生理的覚醒を防ぐ働きがあるのではないかという仮説を立て、その検証に取り組む。それにあたり、二者間コミュニケーション時における両者の視線運動と身体生理活動を同時計測し、それらの相互作用を時系列的に分析することで、相互注視の回避行動の背景にある生理心理学的機序を明らかにすることを目指す。さらに、コミュニケーションの担い手がもつ文化的背景やコミュニケーションの手段といった多様性に潜在するコミュニケーションの質的相違を顕在化することに取り組む。
B01-K211 | 意味・感情の身体表現のエッセンスを探る-ロボットを用いた検証と応用-
上田 悦子 (大阪工業大学 ロボティクス&デザイン工学部)
詳細を見る人が言葉を持たない太古の時代から、祈りや感情、詩など様々なものを伝えるために用いてきた伝達手段の一つである古典舞踊をベースとして、舞踊の身体動作から「同じものを表現する身体動作」をキーとする「意味表現動作プリミティブ」の抽出と、プリミティブを用いて積極的なインタラクションを実現するための「意味を持つ」ロボットの身振り生成手法提案を研究目的としている。
本研究では、このような動作と意味の対応付けの問題をモデルベース手法により解決していく。我々が現有するアジアの古典舞踊8種類・12名分のプロダンサーの意味を表現する動作データ(に加えて古典舞踊動作を追加収集する予定)を、特に表現力の大きい古典舞踊の腕や上半身の動きにターゲットをおいて、(1)動作データを解析し,定量的に意味でカテゴライズした際に有意に分類できる要素(角度の変化や速度など)を抽出し、意味表現動作プリミティブとしての定義を試みる。(2)得られた意味表現動作プリミティブを用いて、小型ヒューマノイドロボット(Alpha1SやPremaidAI)の自由度に応じたヒューマンロボットインタラクション用のロボット動作生成手法を提案する。研究のスタートは、古典舞踊を題材に進めるが、研究後半にはコンテンポラリーダンスでの検証も予定している。コンテンポラリーダンスは、表現者個々の感情やパッションも動作に重なっていると考え、これらの感情やパッションと意味プリミティブとの関係についても考察する。動作に着目して、文化を超えた共通性や逆に越えられない違いを見出し、その結果をロボット動作生成に応用することで、顔・身体学領域研究とロボット工学の融合をめざす。
B01-K212 | パーソナルスペースの定量的な計測方法の開発
小池 耕彦 (生理学研究所 システム脳科学研究領域)
詳細を見るヒトが対面でコミュニケーションをする際には、スキル以前に、最も重要なのはどのような物理的距離で相手と接するかという点である。距離が近すぎれば「馴れ馴れしい」という印象を抱くし、遠すぎれば「よそよそしい」という印象になる。この他者と対面する際の最適な距離は文化圏によっても明らかに異なっており、当然ながら二者の関係性によっても異なっている。この最適な対人距離を理解する、すなわち「パーソナルスペース」として知られている「これ以上近づいてほしくない」という対人距離を理解することができれば、他者とのコミュニケーションの向上に役立てることができるだろうが、主観的な評価以外の方法によりパーソナルスペースを測ることはできていない。申請者は過去に行った研究で、他者がパーソナルスペースの内側に侵入している際に、他者との距離をできるだけ確保するために体が反っており、あたかも他者が存在する「場」が力を発生させて体幹を押しているような状態になっていることに気がついた(Okazaki et al., 2015, PLoS ONE)。この結果、および起立状態が制御される過程を外力の存在する場における倒立振子として理解する研究を組み合わせて、申請者は、パーソナルスペースを他者が存在する場において他者から受ける仮想的な外力として定量化することができるのではないかと考えた。パーソナルスペースどころか2m以内に侵入することができない2020年度開始時点の社会情勢を鑑みて、申請者らの過去の研究で得られた二者対面場面の身体動揺データ(Okazaki et al., 2015)を、社会的な場によって発生する力を受ける倒立振子の動揺というモデルにより説明可能であるかを検討することから研究を始める。次いで、可能であれば対面での実験、もしくはヘッドマウントディスプレイを利用した仮想空間での対面実験により、社会的な場により発生する力というアイデアの妥当性を検証していく。
B01-K213 | トランスカルチャーとしての発達障害者における顔・身体表現
和田 真 (国リハ研究所 脳機能系障害研究部)
詳細を見る発達障害者と定型発達者の間に存在するコミュニケーションの障害は、顔を含む身体特性の違いにもとづいたプロトコルの互換性の問題に起因するという仮説のもと、本研究では、顔・身体認知の時空間的な特徴や、コミュニケーション障害との関連性を明らかにしていきます。その知見を生かすことで、発達障害者と定型発達者との間の「トランスカルチャー」な意思伝達を実現する支援手法の開発を目指します。
これまでの研究では、顔の認知と身体性について自閉スペクトラム症(ASD)者の方の特徴を明らかにしてきました。例えば、ASD者で苦手とされる「雰囲気」の知覚を明らかにするため、感情判断の空間的な特性を調べました。画面中央に提示された顔の印象を答える課題において、感情課題では、周辺顔の影響が促進的に働くことを示しましたが、その効果はASD者とTD者の間で有意な差はありませんでた。一方、全体の印象を答える課題にすると、ASD者の半数で、複数の顔の全体の印象としての感情判断が苦手であることを発見しました(Chakrabarty & Wada, 2020 Sci Rep)。一方、身体性について、皮膚ラビット錯覚をもちいることで、自閉スペクトラム症(ASD)の障害当事者の三分の一以上の方で、触知覚が身体外に定位されにくく、それ故に道具の身体化が困難である可能性を明らかにしました(Wada et al., 2020 Sci Rep)。このように、ASD者では、顔・身体の認知特性がTD者とは異なることがわかってきましたが
、その統合的な理解は進んでいません。しかも、コミュニケーション障害の原因は、そこに潜んでいる可能性が高いと推測されます。本研究では、顔・身体について、定型発達者とのプロトコルの違いを補完することで、発達障害者と定型発達者の間の「トランスカルチャー」な意思伝達を実現することを目指します。
B01-K214 | 扁桃体神経活動が霊長類の顔認知・情動反応・視覚皮質神経活動に及ぼす影響
宮川 尚久 (量研機構放医研脳機能イメージング)
詳細を見る私たちヒトの社会的コミュニケーションを支える顔の視覚認知処理の神経機構は、腹側視覚皮質を中心に理解が進められてきた。一方、これまで情動に関連する脳領域とされてきた扁桃体が、顔や表情、視線などを素早く検知することから、無意識における顔情報処理に重要な役割を果たす可能性が示唆されているが、その詳しい実態は不明である。本研究は、扁桃体が腹側視覚野と連関して、顔や表情、視線の視覚情報処理と情動身体反応の相互作用を実現する仕組みについて、知覚、神経情報処理機構、身体反応の3つの側面から統合的に明らかにすることを目的とする。そのため、ヒト同様側頭葉が発達したマカクザルを対象とし、代表者らがこれまで開発した広範囲で神経活動を計測するECoG記録法と、現在成果を挙げている最新の化学遺伝学による脳活動操作とイメージングの融合技術により、次の3項目について特定する。
1)顔・表情知覚 :扁桃体―顔パッチ連関が顔知覚に果たす役割
2)神経基盤:扁桃体―顔パッチ連関の実態=顔・表情の神経情報処理と神経回路
3)身体反応:扁桃体―顔パッチ連関が顔・表情認知に伴う情動反応に果たす役割
具体的には、①標的部位の神経活動を一定時間、繰り返して抑制することができる化学遺伝学(DREADD)受容体hM4Diをマカクザル扁桃体に導入することで、扁桃体―顔パッチ連関を遠隔操作する。②腹側視覚皮質に脳表型電極(ECoG)を留置し、扁桃体―顔パッチの神経情報処理を解析する。③サルに顔・物体を提示したり、弁別課題を遂行させ、扁桃体―顔パッチ連関の操作による動物の知覚判断および情動的身体反応(例 瞳孔径変化や発汗など)を解析する。
B01-K215 | 顔・身体表現の情報工学に基づくトランスカルチャー比較
林 隆介 (産業技術総合研究所 人間情報研究部門 ニューロリハビリテーション研究グループ)
詳細を見る顔と身体表現の異文化を作りあげるメカニズムの一つとして、各コミュニティー内での発達過程における視覚体験の違いがあげられる。視覚体験の違いが、脳内情報表現にどのような違いを引き起こすのか情報工学的に解明することは、赤ちゃんを用いた発達研究や異文化間の比較心理学的研究とならんで、顔・身体学の構築に不可欠な研究アプローチである。本研究では、脳のモデルとして、深層ニューラルネットワーク(Deep Neural Network, DNN)を仮定し、大規模な顔・身体画像データを教師なし学習したとき、どのような顔・身体情報表現が自己組織的に獲得されるのかを明らかにする。そして、文化による画像統計量の変化と、獲得される顔・身体情報表現の違いを定量的に解析することにより、文化の影響を作り上げる基礎的メカニズムの解明をめざす。
これまで、本学術領域に前期公募班員として参画し、独自に開発したDNNの教師なし学習により、脳と類似した階層的な特徴抽出が実現できることを明らかにした。生物学的に妥当なDNNの学習原理が設定されているのであれば、DNNの情報表現を解析することで、脳における顔や身体表現の手がかりが得られると期待される。そこで、後期公募班研究では、DNNの教師なし学習によって獲得される、各階層における視覚情報処理の諸特性を明らかにすることを最初の目標とする。
そして、本新学術領域の他班メンバーと協力して、さまざまな文化圏から顔・身体・環境画像ならびに言語情報を収集し、DNNの文化別学習ならびに機械学習手法を駆使し、文化間の情報表現形式を比較検討することで、文化差の定量化と文化差を生み出す基礎的メカニズムの科学的解明研究を推進したいと考えている。
C01-K201 | Embodiment, Ethics, and Humanism: The Face-Body Studies of Colonial Cinema
小田桐 拓志 (金沢大学国際基幹教育院)
詳細を見るThis research project examines humanism as a theoretical-phenomenological framework for face-body studies in transcultural conditions, with a dual focus on ethics and media studies.
The premise of this project is that face-body experience is fundamentally ethical. While behavioral sciences (e.g., psychology and neuroscience) study facial-bodily communication as a value-neutral phenomenon, this project focuses on normative or value-laden aspects meaningful to the subject, such as power, hegemony, and moral responsibility. The project will involve creating a visual ethnography of body images that will include philosophical
reflections inspired by various phenomenological or critical texts. In particular, the project attempts to show that humanism, which is subconsciously represented in embodied images, is both historically and conceptually connected to coloniality. The project will evaluate a few claims. Our experiences of being human are ethical or colonial constructs (Fanon), constituted by our bodily-facial images (of human beings). This embodied ideology of humanism is formed through the affective “haptic” (Marks) perception of our human self-images. Since the body is a contingent construct open to cultural interpretations, images of the body signify our colonial gaze toward the colonized and the animalistic. By evaluating these claims, the project investigates how coloniality and humanism are embedded in images (or conceptions) of the human body.
C01-K202 | 「能」における感情移入と共同性の哲学的探求-面(顔)と所作(身体)を中心に-
小谷 弥生 (日本女子大学 学術研究員)
詳細を見る本研究は「顔・身体学」における根本問題として、「顔とは何か」、「身体とは何か」、そして「顔・身体とは何か」という問いを位置付け、哲学の視点よりこれらを探求することを基礎としています。具体的には、これまで断片的な理解にとどまってきた「能」を研究対象とすることで、「顔・身体学」が目指す〈顔と身体表現の無意識を意識化することによる、他者及び異文化理解の試み〉を実現するべく、哲学的探求による共有可能な理論化に取り組み、〈日本発の新たな研究領域の構築〉への貢献を目指しています。
「能」は、本来生身の感情の場である顔を覆い隠す仮面劇であるにもかかわらず、その「面」はときに生身の顔以上に、多彩かつ微細な感情を感受しうる対象となります。しかし「能」の極致である《花》が舞である以上、「能」より感受する感情とは、面(顔)のみならず所作(身体)と共に思考されなければ、真の理解は得られないはずです。この点を踏まえ、〈顔としての「面(おもて)」〉と〈身体表現としての「所作」〉の双方より、複合的な検討を行います。
加えて、「能」は観客と共に演出される(共同演出)とも言われますが、能舞台において表現される感情は、いかにして観客に感受され、また共同演出を実現するのでしょうか。本研究は前身として、世阿弥の能楽理論に記される「離見の見(りけんのけん)」のうちに、能楽師によって体現される自我の超越性を見出すとともに、感情移入を可能化する共同性や相互主観性を観取・探求してきました。この研究経緯・成果を踏まえ、本研究は「能」の舞台空間における感情をひとつの出来事として捉えるとともに、主観性、共同性、劇空間におけるドラマと現実化運動の分析などを軸とし、「顔」「身体」そして「顔・身体」について検討します。こうした問題意識に立脚しつつ、「顔・身体学」が提起する3つの位相(個人内・外・間)において、その共通性と異質性、相互性について、多層的な研究を行います。
C01-K203 | トランスカルチャー状況下における身体化された自己
田中 彰吾 (東海大学現代教養センター)
詳細を見るこの公募班では、グローバル化した現代社会において「日本的自己」がどのように変化しつつあるのか(または変化していないのか)、身体性の観点から解明することを目的としている。本研究が依拠するのは現象学と認知科学の学際領域で発展してきた「身体化された自己」の理論であり、身体と環境の相互作用から創発する現象として自己を理解する。1970年代に現れた日本的パーソナリティ論(たとえば「甘え」理論)や、1990年代に展開された比較文化心理学にもとづく自己論(たとえば「相互依存的自己」の理論)は、いずれも日本的自己の関係依存的な特徴を指摘してきた。これらは貴重な考察を含むものの、「欧米文化vs日本文化(非欧米文化)」という二分法的な図式を暗に引きずっており、日本文化に固有の変わらない本質があることを前提としているように見える。
本研究では、身体性に着目することでこのような図式的・本質的な見方を避け、身体的経験への焦点づけの違いによって、文化的自己がさまざまなしかたで構築されうることを理論的に明らかにする。日本の社会的慣習には、対人場面で知覚・評価される身体(他人からどう見られるか)を強調する傾向がある。このような身体的経験への焦点づけは、他者による評価を強く内在化させて自己を形成する契機になっている。哲学者J-P・サルトルは「客体としての身体」という概念に沿って、このような身体経験と自己の関連を現象学的に記述している。本研究では、まず、サルトルの身体論に沿って「日本的自己」の関係依存的な特徴を改めて記述し直す。次に、この理論研究を踏まえて、ハワイに在住する日系移民へのインタビュー調査を実施する。ハワイは米国の一部でありながらアジア諸国から多くの移民を受け入れてきた歴史を持ち、グローバル化の過程で多文化が混淆する現代のトランスカルチャー状況を具現する地域である。調査の焦点は、ハワイの日系移民が、日本の在住者と比較して、どのように異なるしかたで文化的自己を構築しているのか、という点である。調査においては、衣服やタトゥーなど「客体としての身体」をめぐる人々の社会的実践に注目し、文化的自己に迫る予定である。
C01-K204 | 障害者と家族間における文化の独自性の解明:家庭内/外相互行為の分析を通して
牧野 遼作 (広島工業大学 情報学部)
詳細を見る私たちの日常生活は、様々な場所で、様々な他者との相互行為によって営まれている。このような相互行為の中で、人々は「相手が理解可能な形で振る舞い」、かつ相手の振る舞いを理解した上で他者の振る舞いに連ねるように振る舞う。例えば、人々が立ち話をするとき、相手の位置や移動に合わせ、自身の立ち位置を決め、変化させる。この相互調整を通して、「相手を見ることができ、相手の発話を聞くことができる」かつ「相手が自身を見ることができ、自身の発話を聞くことができる」ように、人々は立ち話のための陣形を形成・維持している。人々の日常的な相互行為は、周囲の環境や人々の特性に合わせて調整され変化する。単なる立ち話ではなく、展示物解説のようなモノを交えての会話であれば、対象となるモノが適切に見えるように相互調整がなされる。また(大人よりも背の低い)子供を交えた会話であれば、相手の目線の高さに合わせるように姿勢の変更といった調整がなされる。
人々の相互行為における周囲の環境・人々の特性に合わせた相互調整のやり方の検討の一環として、本研究では、身体知的重複障害者と家族の日常的相互行為を対象に、相互行為における振る舞いの詳細な記述に基づく定性的「相互行為分析」を行う。特に家庭内と家庭外で起こる相互行為を対象にビデオ収録・分析を実施する。家庭内の相互行為は、彼らの身体特性に合わせ生活環境の中で行われる。この身体特性と生活環境に調整された相互行為を収録・分析することを通して、家族内の独自の相互行為のやり方(=家族という小集団における独自の文化)を明らかにする。また家庭外において障害者-家族が他者と出会う場面の収録・分析を行うことで、彼らの相互行為の独自性がどのように変容し、その場その時の相互行為を展開しているかを検討する。これらの検討を通して、障害者-家族が、その集団内で独自の文化を持つこと、またその文化は他者と出会う中で、柔軟に変化しう
ることを明らかにする。
C01-K205 | 表情・身体動作の理解と一人称報告の信頼性に関する哲学的・経験科学的研究
長滝 祥司 (中京大学 国際学部)
詳細を見るわれわれは、他人の表情や身体動作からその人の心的状態を直観的に理解したり、性格傾向などを把握したりすることがある。こうした素朴心理学的能力を解明し精緻化しようとする学問上の関心も、科学革命の時代の観相学や感情学から、19 世紀の骨相学やダーウィン進化論を経て20 世紀の精神分析、一部の感情心理学へと続いている。これらの学問で使われていたのは、基本的には日常の人間観察と当人の内観による一人称的報告である。本研究では、素朴心理学をめぐる以上の流れに配慮しつつ、現代の現象学や心の哲学を理論的背景として、実証的方法によって得られたデータを用いながら、意識的、無意識的な表情・動作表出やそれらによる他者理解のメカニズムの解明をめざす。その際、一人称的報告の信頼性についても、脳科学的データによって擁護する。
また、表情・動作表出と理解の職業文化的差異や文化間の違いにも実験的な手法を用いて解明の光をあてる。
具体的には、(ア)観相学や感情学からダーウィンの表情論などに至る近代以降における素朴心理学の精緻化の歴史を哲学的・思想史的観点から掘り下げ、日常経験を捉える現象学の理論や心の哲学との比較研究を行う。(イ)心理学的、脳科学的な実験を遂行し、そこで得られたデータを(ア)の知見に照らし合わせて分析し、(ウ)客観主義(科学的方法)と(ラーファター的な)主観主義を総合するような方法論を構築する。(ア)の比較研究においては、具体的な事例を記述するターミノロジーに注目して、哲学史において素朴心理学的事象がどのように捉えられてきたかを精査する。ただし、現象学と心の哲学のターミノロジーや方法論の違いには注意を払う必要がある。この二つを架橋しようとする際に、特に後者においてデカルト主義に基づく二元論的発想の残滓がある点には留意する。(イ)においては、内観による一人称報告の意義や射程を明らかにすることを念頭に置いている。(ウ)が本研究のもっとも大きな課題であるが、(ア)であげた哲学的な成果を素朴心理学的なターミノロジーの精緻化にどう反映させ、またそれを科学的データ(特に脳科学のデータ)にどう関連付
けていくか、ということが問題となる。
C01-K206 | 縄文・弥生時代のトランスカルチャー状況(地域間交渉)と「顔・身体」装飾付土器
中村 耕作 (國學院大學栃木短期大学)
詳細を見るみなさんは縄文土器と言えば「火焔土器」に代表するような立体的な複雑な文様をイメージされるかと思います。確かに、縄文土器は、現代のわれわれから見ると過剰・複雑な装飾を施すことがあり、その1つの方法として、顔や身体を表現することがあります。土器に土偶のような造形を貼り付けることもあれば、土器自体を身体に見立てて顔などを付す場合もあります。
本研究が注目しているのは、それらが、縄文時代後半期~弥生時代前半期の中でも、限られた時期・地域に集中して作られていることです。実はその時期は、文様の特徴から推測される各地域の集団の交流が活発化した時期に当たります。土器づくりでも各地の手法を折衷したり、遠方の文様を持った土器が見つかったりしているのです。私は、この時期こそ、縄文世界における「トランスカルチャー状況」ではないかと考えました。
そこで、本研究では、こちらの共同研究で培われた視点を導入し、この現象を説明してみたいと公募研究に応募したのです。それまで抽象的な文様が多かったのに対し、交流が活発化すると「顔・身体」を表現したのはなぜでしょうか。現時点では、社会がより複雑化する中で、より強力なメッセージを持ったイメージ(造形)が求められたのかと考えています。
具体的な検討内容としては、縄文~弥生時代の「顔・身体土器」を対象に、1)従来の「これは顔か顔でないか」という二分法ではない段階的な指標を作り、2)事例の集成による変化の量的な把握を行い、3)顔・身体土器増加期の社会的な変化との比較を行います。そして、この個別研究の成果を、心理学や文化人類学をはじめとする本領域の研究者の皆さんの知見とつきあわせ、また考古学のもつ長期スパンの変化の知見を提供しながら、人間とモノと、その境界域にある「顔・身体造形」を中心とした新たな顔・身体の考古学(物質文化研究)の構築の基盤づくりを目指したいと考えています。