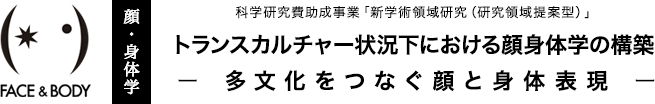研究組織
公募研究
A01-K101 | 顔色-表情知覚の相互作用の文化・世代間比較
南 哲人 (豊橋技術科学大学エレクトロニクス先端融合研究所)
詳細を見る
近年、顔の形状情報以外に、顔色や反射特性など顔の表面情報も顔認知に重要な機能を果たしていることが示されてきている。われわれは、これまで、心理物理実験を始め、脳波やfMRI等の神経科学的手法を用いて、統合的に顔色情報にアプローチし、顔色の処理が刺激呈示後170msに生じ、その処理に左紡錘状回顔領域が関与することなどを明らかにしてきた。さらに、「顔を真っ赤にして怒る」というような慣用句に表現されるように、顔色が表情認知にどのような影響を与えるのか調べてきた。具体的には、2つの表情をモーフィングし、あいまいな表情画像を作成した上で、顔色を操作することにより、表情判別が変化するかどうかを調べた。表情認知に顔色が影響を与えるのであれば、あいまいな表情の判断を行う場合に顔色の情報が大きく影響を及ぼすと考えられる(例えば、怒っているのか、怯えているのかがあいまいな表情の場合、顔色が赤みを帯びていれば怒りの表情と判断されやすくなる)。その結果、顔色と表情知覚が相互に作用していることを示した。ただし、この実験は、日本人の20代を中心とした実験協力者を対象としたものであった。霊長類の色覚の進化的観点からも顔色の重要性が示唆されていることから、顔色は日本人にとどまらず、ヒトの適応一般に共通する情報源であると考えられる。その一方で、顔認識において他人種効果と呼ばれる民族や人種が異なる顔の認識や識別が困難となる現象が存在するため、顔色への感受性において民族や人種間の差異が存在する可能性もある。そのため、文化間、世代間比較をして、顔色の効果を調べる必要がある。そこで、本研究では、顔色と表情認知の相互作用に関わる心理物理学実験を、文化間、世代間で横断的に行い、その普遍性・特異性を調べる。
A01-K102 | 牧畜民社会における感情の身体表現とその変化:東アフリカ・マサイの事例から
田 暁潔 (筑波大学体育系 / 京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科)
詳細を見る
感情をテーマにしてきた多数の心理学者が、「怒り」、「恐れ」、「嫌悪」、「悲しみ」、「喜び」といった五つの感情を、文化の枠を超えてすべての人類に見られる普遍的なものとして認識している (Ekmen, 2016)。その一方、表情やジェスチャーなどによって表現される感情は、地域文化に強く依存しており、身体的なメッセージがいかに認識されるのかについて理解することは、円滑なコミュニケーションが成立する上で不可欠である。しかし、これまでの研究の多くは、工業先進国や狩猟採集社会などの限られた地域集団しか対象にしておらず、社会変化による感情の示し方の変化についての議論も十分にされてこなかった。
本研究では、牧畜民マサイを対象に、近代的な開発や学校教育、土地の私有化などによって激しく変化するマサイ社会において、対面的・非対面的な状況でおこなわれているインタラクションに五つの感情がいかなる表情とジェスチャーによって表出・認識されるのかを実証実験的な調査によって明らかにする。具体的には、都会、マサイの町、村落三つの環境で生活を営むマサイから、それぞれ性・年齢の異なる人々を対象とし、日常における対面的・非対面的な相互行為から五つの感情にかかわる表情とジェスチャーを、それらがどのような状況において発生したのかと併せて、写真やビデオなどによって収集・分類・分析する。また、収集した身体表現とその状況をリストアップして、実験調査に用いるテストを作成し、前述の三つの地域のマサイそれぞれに、自分たちと異なる地域で収集された身体メッセージとそれらによって表された感情を認識してもらう。さらに、感情が発生する状況を選択肢から選んでもらい、これらの実験から得られたデータの整理・分析によって、同じ牧畜文化集団における感情の身体的表現と、それらの共通点・相違点を明らかにする。
本研究では、牧畜民マサイを対象に、近代的な開発や学校教育、土地の私有化などによって激しく変化するマサイ社会において、対面的・非対面的な状況でおこなわれているインタラクションに五つの感情がいかなる表情とジェスチャーによって表出・認識されるのかを実証実験的な調査によって明らかにする。具体的には、都会、マサイの町、村落三つの環境で生活を営むマサイから、それぞれ性・年齢の異なる人々を対象とし、日常における対面的・非対面的な相互行為から五つの感情にかかわる表情とジェスチャーを、それらがどのような状況において発生したのかと併せて、写真やビデオなどによって収集・分類・分析する。また、収集した身体表現とその状況をリストアップして、実験調査に用いるテストを作成し、前述の三つの地域のマサイそれぞれに、自分たちと異なる地域で収集された身体メッセージとそれらによって表された感情を認識してもらう。さらに、感情が発生する状況を選択肢から選んでもらい、これらの実験から得られたデータの整理・分析によって、同じ牧畜文化集団における感情の身体的表現と、それらの共通点・相違点を明らかにする。
A01-K103 | 身体化された情動の文化化を探る―中国雲南省少数民族の身体的心性―
山田 祐樹 (九州大学基幹教育院)
詳細を見る
認知心理学において,近年「身体化された情動」に関する研究が注目されている。例えばヒトの身体を中心とした上下空間に情動が関連付けられることが示されており,上=快,下=不快という関係性は極めてロバストに,文化普遍的に観察されてきた。しかし従来の研究は文明化された地域しか対象とせず,比較的広い地域の人々からの平均的な行動反応を取得していた。しかしある少数民族における歴史的経緯を考慮すると,これまでの知見とは全く異なった様相が呈される可能性が考えられた。
本研究では中国雲南省のアカ族を主な対象とする。彼らは歴史的に低地に居住することを望みながらも,高地に「逃れざるを得なかった」人々である。すなわち,一般的な上=快,下=不快とは真逆の状況にてその文化を形成してきた。本研究は彼らとその他の部族集団(ハニ族,タイ族)との比較によって,歴史的文脈が異なることによる身体化情動の違い,いわば「身体化された情動の文化化」について検討するものである。今こそ本研究によって初めて「身体化された情動のフィールド実験研究」を実施する時が来たのである。
具体的には,シーサンパンナ州の南糯山と格朗和に滞在してアカ族への調査・実験を行う。また景洪市全域にてタイ族に対しても同様のことを行う。さらに,紅河ハニ族イ族自治州の元陽に滞在してハニ族への調査・実験を行う。
本研究では1)アカ族,2)ハニ族,3)タイ族それぞれの(A)高齢者・(B)若年者の計6グループを対象とした,半構造化フォーカスグループインタビューによる質的研究と,単語定位-評定課題による量的研究を組み合わせた説明的順次的デザインに基づく混合研究法を用いる。量的研究ではタブレットを刺激呈示・記録デバイスとして用いるが,対象部族集団は文字を持たないため単語刺激は口頭で呈示する。これらの量的・質的データの両方を統合して結果の解釈を行う。
本研究では中国雲南省のアカ族を主な対象とする。彼らは歴史的に低地に居住することを望みながらも,高地に「逃れざるを得なかった」人々である。すなわち,一般的な上=快,下=不快とは真逆の状況にてその文化を形成してきた。本研究は彼らとその他の部族集団(ハニ族,タイ族)との比較によって,歴史的文脈が異なることによる身体化情動の違い,いわば「身体化された情動の文化化」について検討するものである。今こそ本研究によって初めて「身体化された情動のフィールド実験研究」を実施する時が来たのである。
具体的には,シーサンパンナ州の南糯山と格朗和に滞在してアカ族への調査・実験を行う。また景洪市全域にてタイ族に対しても同様のことを行う。さらに,紅河ハニ族イ族自治州の元陽に滞在してハニ族への調査・実験を行う。
本研究では1)アカ族,2)ハニ族,3)タイ族それぞれの(A)高齢者・(B)若年者の計6グループを対象とした,半構造化フォーカスグループインタビューによる質的研究と,単語定位-評定課題による量的研究を組み合わせた説明的順次的デザインに基づく混合研究法を用いる。量的研究ではタブレットを刺激呈示・記録デバイスとして用いるが,対象部族集団は文字を持たないため単語刺激は口頭で呈示する。これらの量的・質的データの両方を統合して結果の解釈を行う。
A01-K104 | 美しい/かわいい/不気味:顔情報変異の布置を用いたヒト普遍性/文化間変異の検討
橋彌 和秀 (九州大学 人間環境学研究院)
詳細を見る
本研究は、顔刺激(形態)が持つ「美しさ」「かわいさ」そして「不気味さ」という属性に着目し、これらの印象を喚起する顔刺激特徴の関係について、合成顔をもちいた実験によって検討する。従来別個に扱われがちだった「美しい」「かわいい」「不気味」という反応の相互関係を、顔というプラットフォーム上に付置することによって統合することを目指している。方法論における大きな特徴は、合成顔の素材として「オトナの顔」―「コドモの顔」をもちいる軸に「ヒトの顔」―「非ヒト(たとえば類人猿)の顔」という軸を加えて直交させ、仮想平面上で合成の比率を連続的に変化させて、被験者自身が操作するタブレット上で刺激を構成する手法を創案し採用する点にある。生物学的背景として想定される「配偶者選択」「養育」「生物学的同種集団維持」等の適応上の要請に顔情報の微細なベクトルがどのように寄与するかを統合的に解明し包括的な展望を提示するためには、文化・社会間の変異/普遍性に特に注目してアプローチする必要があるため、文化比較・発達研究を計画に含め、この研究手法を多様な文化圏で適用し、並行して、幼児・学童児を対象とした研究へと展開する。
研究メンバー
- 小林 洋美 (九州大学 人間環境学研究院 / 研究協力者)
- 齋藤 慈子 (上智大学 総合人間科学部 心理学科 / 研究協力者)
A01-K105 | 顔・身体表現から検討するトランスカルチャー下の装飾美
山本 芳美 (都留文科大学文学部比較文化学科)
詳細を見る
本研究計画は、研究代表者の山本芳美(都留文科大学)、研究協力者の桑原牧子(金城学院大学)、津村文彦(名城大学)、大貫菜穂(京都芸術造形大学)、南玲子(日本文化人類学会)、山越英嗣(早稲田大学)、Matt
Lodder(University of Essex)の7名で構成される国際共同研究である。この研究では、多文化的、トランスカルチャーの状況を踏まえて各文化の装飾を比較する。「研究A」と「研究B」の2班にわかれて実施し、山本、桑原、津村の「研究A」では、イレズミやボディペインティング、化粧ほか、各種身体変工に魅力を感じさせる装飾パターンがあるのかを考察する。文化人類学的なアプローチから、各調査地での写真、画像などを資料として、イレズミとボディペインティング、化粧を主軸に多文化間の比較を試みる。山本、大貫、Lodderの「研究B」では、日本のイレズミの図柄に特化した研究をおこなう。日本とその影響を受けたと考えられる19世紀末から20世紀初頭にかけての海外のイレズミの図案の分析と国内外で活躍した日本人彫師の研究に特化した研究である。それぞれがすでに進めてきた研究を基盤とし、さらにそれを他の研究者との交流で発展させることで、着実に成果につなげることとしたい。この研究は、現在に各地に残る日本のイレズミと日本風とされる図案を分析し、図案に対して日本や西洋の絵画のどのような要素と融合して新しい図案や表現が生み出されたのかを表象論・美術史の視点から解析する. 研究成果は、中部人類学会談話会、日本文化人類学会、美学会、その他の学会で発表するとともに、公開シンポジウム等にて一般にも発信する予定である。
研究メンバー
- 桑原 牧子 (金城学院大学文学部外国語コミュニケーション学科 / 研究協力者)
- 津村 文彦 (名城大学 外国語学部 / 研究協力者)
- 大貫 菜穂 (京都造形芸術大学 / 研究協力者)
- Matt (Matthew) Lodder (University of Essex / 研究協力者)
- 秦 (南) 玲子 (日本文化人類学会 / 研究協力者)
- 山越 英嗣 (早稲田大学人間研究センター / 研究協力者)
A01-K106 | ミニマルな顔表現の文化的差異に関する研究
金谷 一朗 (長崎県立大学情報システム学部)
詳細を見る
ミニマルな顔表現は世界各地で見られるデザインであり,かつヒューマノイドのような人に似せた人工物デザインの基本になるものである.しかしながら,ミニマルな顔表現およびその変化に対して,表現と感情との対応付けやその文化的差異を詳しく調べた研究は少なく,工業応用への研究は緒についたばかりである.本研究提案は幾何学的に抽象化された顔,すなわち「左目」「右目」「口」に相当する図形要素3点からなる「ミニマルな顔表現」および「ミニマルな顔表現の動き」と,それらの顔表現と感情との対応の文化的差異を明らかにすることを目的とし,人工物デザインへの応用までを考慮する.本研究提案者らはすでに日本において予備的な調査を済ませているが,本研究提案にあわせて新たに日本での再調査を行うため,本再調査を含めて,研究期間内に(1)日本での再調査,(2)東アジアから1カ国の調査,(3)中東から1カ国の調査,(4)西欧から1カ国の調査を行う.具体的な調査内容は(A)複数のミニマルな顔表現を提示し,被験者が感情を読み取る「静的ミニマル表現マッピング」,(B)ミニマルな顔表情の「動き」を提示し,被験者が感情の「動き」を読み取る「動的ミニマル顔表現マッピング」,(C)ミニマルな顔を被験者に描かせる「顔表現サンプリング」である.本調査を研究期間内に行い,統計処理および機械学習によってミニマル顔モデルの構築を行う.本研究提案は今後急速に進歩,普及するとみられるヒューマノイドロボットの顔表現,顔デザインに関するものである.工業生産的にはロボットハードウェアはシンプルな方が好ましく,ヒトの顔もまた世界各地で異なる傾向があるため,工業デザイン的にもミニマルな要素を組み合わせたほうが世界各地の顔を模倣するよりも好ましい.一方で,顔の作り出す表情というソフトウェアの側面は,文化的に極めて重要であるにも関わらず,従来は工業デザイナあるいはエンジニアによる直感と経験とに頼ってデザインされてきた.本研究提案は従来の直感と経験に頼っていた部分に秩序と方法をもたらすことで,ヒューマノイドロボットの工業生産,工業デザインに対して世界的なインパクトを与えるとともに,ヒトが顔をどのように認知しているかという問題に対してヒントを出す役割も併せ持つ.
研究メンバー
- 山本 景子 (京都工芸繊維大学 大学院工芸科学研究科 / 研究協力者)
B01-K101 | Non-verbal communication through yawning
Tseng Chiahuei (東北大学電気通信研究所)
詳細を見る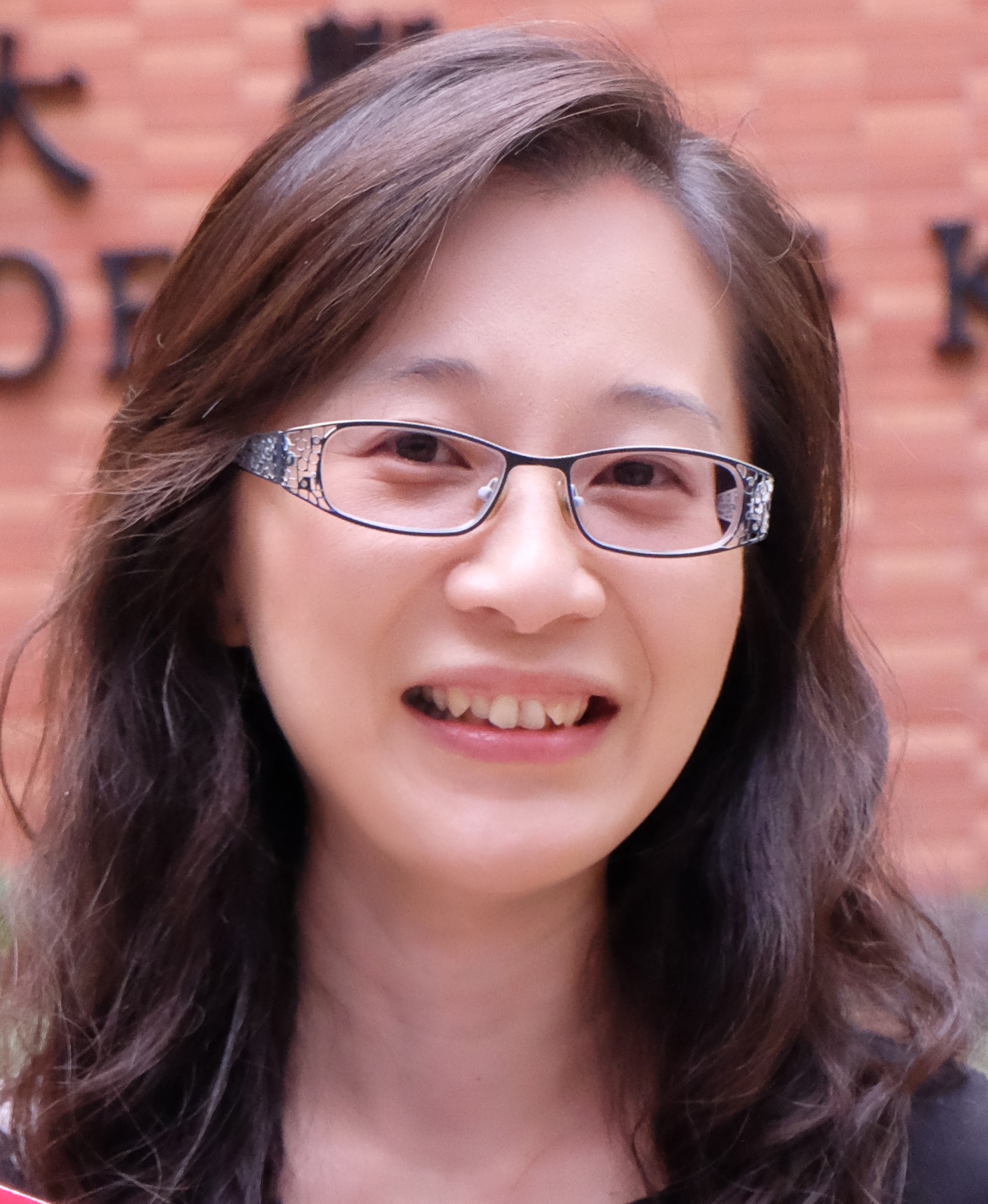
Yawning is a universal phenomenon across cultures, vertebrate species, and developmental stages. We test the social-communication hypothesis of yawning which suggests that yawning is a non-verbal form of communication that synchronizes the behavior of a group. We design hypothesis-driven experiments with behavioral and physiological measurements to investigate the social benefits and the underlying mechanism of yawning and its contagion effect. This is in contrast to the previous studies which are mainly conducted with observational or correlational methods.
Although yawning has very different meanings in the western and eastern cultures, surprisingly, there is little cross-culture comparison studies. As non-verbal expressions help an observer to deduce a group’s norm and social value when entering into a new context and culture, studies in this direction are warranted. Our studies will be extended to cultural group comparisons between Japan, Taiwan, and UK as it offers a convenient platform to tap into the inter-cultural understanding.
Although yawning has very different meanings in the western and eastern cultures, surprisingly, there is little cross-culture comparison studies. As non-verbal expressions help an observer to deduce a group’s norm and social value when entering into a new context and culture, studies in this direction are warranted. Our studies will be extended to cultural group comparisons between Japan, Taiwan, and UK as it offers a convenient platform to tap into the inter-cultural understanding.
研究メンバー
- 塩入 諭 (東北大学電気通信研究所 / 研究協力者)
- 佐藤 一文 (東北大学大学院情報科学研究科 / 研究協力者)
B01-K102 | 計算論的行動計測技術に基づく顔と身体表現における物理的対面の機能とその障害の解明
松田 壮一郎 (筑波大学人間系)
詳細を見る
視線は刺激と反応、2つの機能共に顔・身体表現の基盤であり、対人相互コミュニケーションで重要な役割を果たす。本研究ではウェアラブルデバイス、モーションキャプチャシステム、視線推定などの計算論的行動計測技術に基づき、情報工学や臨床発達心理学と緊密に連携をしながら、アイコンタクトとは異なる、認知科学的に新しい現象としての物理的対面の機能とその障害の解明を目指し、系統的な実験研究を実施する。
(1). 物理的対面の機能的役割解明:会話場面における相互作用場面で、話し手・聞き手双方の物理的対面とアイコンタクトの同時計測実験を行う。会話時の質問/回答やゲームの交互交代時に計測を行い、物理的対面・アイコンタクトの頻度、タイミングや持続時間の解析を通じ、物理的対面の言語コミュニケーションにおける機能について検討する。また、二者間の相対的位置関係、二者間距離、発話(質問)内容、相手の親密性などの空間・社会的要因の影響を明らかにする。
(2). 物理的対面の障害解明:共同注意・行動的要求・社会的相互作用の場面で、自閉症児・療育者双方の物理的対面とアイコンタクトの同時計測実験を行う。社会的行動の始発/応答時に計測を行い、社会性に障害のある自閉症スペクトラム障害(ASD)児と定型発達児間の比較を通じ、物理的対面の非言語コミュニケーションにおける機能とその障害について検討する。
本研究を通じて、アイコンタクトと物理的対面の機能分離を目指す。同時に、ディスプレイを媒介した対面・アイコンタクトではない、物理的対面下における二者同時計測という実験手法から、「見る/見られる」といった社会的行動の機能の身体性を明らかにし、新たな実験パラダイムの構築を目指す。
(1). 物理的対面の機能的役割解明:会話場面における相互作用場面で、話し手・聞き手双方の物理的対面とアイコンタクトの同時計測実験を行う。会話時の質問/回答やゲームの交互交代時に計測を行い、物理的対面・アイコンタクトの頻度、タイミングや持続時間の解析を通じ、物理的対面の言語コミュニケーションにおける機能について検討する。また、二者間の相対的位置関係、二者間距離、発話(質問)内容、相手の親密性などの空間・社会的要因の影響を明らかにする。
(2). 物理的対面の障害解明:共同注意・行動的要求・社会的相互作用の場面で、自閉症児・療育者双方の物理的対面とアイコンタクトの同時計測実験を行う。社会的行動の始発/応答時に計測を行い、社会性に障害のある自閉症スペクトラム障害(ASD)児と定型発達児間の比較を通じ、物理的対面の非言語コミュニケーションにおける機能とその障害について検討する。
本研究を通じて、アイコンタクトと物理的対面の機能分離を目指す。同時に、ディスプレイを媒介した対面・アイコンタクトではない、物理的対面下における二者同時計測という実験手法から、「見る/見られる」といった社会的行動の機能の身体性を明らかにし、新たな実験パラダイムの構築を目指す。
研究メンバー
- 蜂須 拓 (筑波大学システム情報系 / 研究協力者)
- 辻 愛里 (筑波大学システム情報系 / 研究協力者)
- 鈴木 健嗣 (筑波大学システム情報系 / 研究協力者)
- 山本 淳一 (慶應義塾大学文学部 / 研究協力者)
B01-K103 | 顔の色と情動認識の異文化比較
溝上 陽子 (千葉大学大学院工学研究院)
詳細を見る
顔の色や質感は、年齢、健康状態、印象、審美性など、人間にとって重要な判断に大きく関わる。しかしその認識特性は、従来の色彩学の知見が当てはまらないことが多い。例えば、日本人女性の顔を用いた研究では、顔の明度が等しい場合でも、赤みを帯びた顔は黄みを帯びた顔よりも明るく見えることが示されている。このような肌色特有の知覚は、肌の色の分布特性や肌色変化を認識するための特別な視覚メカニズムによって引き起こされると考えられる。 前述の通り、顔色は健康状態や感情を読み取る情報となるが、実際に私たちがどの程度敏感に顔色を知覚しているか、そこからどの程度情動を読み取れるのかについては明らかではない。また、人種や文化により、顔の色分布や色変化の仕方および表情の出方が異なることから、それらが顔の色知覚と情動認識の関係にも影響する可能性がある。そこで本研究では、顔の明るさ認識に対する色相の影響、顔色の識別能力、顔色の変化に基づく情動判断、それぞれに対する人種・文化の違いを検討する。 期間中に下記の課題に取り組む計画である。1. 顔の明るさに対する色相の影響の異文化比較2. 顔色の識別能力の異文化比較3. 顔色変化が情動の認識に与える影響の異文化比較 複数の人種の顔を評価刺激画像として用い、日本、欧米、東南アジアなど、様々な国で、顔の明るさ認識、顔色の識別、情動認識を調べる視覚評価実験を行う。その結果を比較することにより、異文化間に共通の顔色の認識特性があるかを調べる。また、その観察時の脳活動と認識との対応関係についても調べる。 本研究により、「顔色知覚特性」と「顔色知覚と情動認識の関係」に対する異文化の影響が明らかになれば、グローバル社会における円滑な異文化コミュニケーションおよび化粧品、写真、医療など、多岐に渡る分野に貢献できると考えられる。
研究メンバー
- 菊地 久美子 (資生堂グローバルイノベーションセンター / 研究協力者)
- 山田 真希子 (国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 放射線医学総合研究所(放射線医学総合研究開発部門) 脳機能イメージング研究部 / 研究協力者)
B01-K104 | 社会的相互作用を支える無意識の対人間協調ダイナミクス
三浦 哲都 (東京大学大学院総合文化研究科)
詳細を見る
社会相互作用を探るヒトの二者間運動協調の研究は、二人が座位で手に持った振り子を合わせる協調運動課題によって検討されてきおり、顔が与える影響については検討されていない。近年、二者が向かい合って立つと姿勢動揺が無意識的に同期することが報告され、この同期が社会相互作用を支える神経系の機能として注目され始めている。しかしながらこれらの研究は、姿勢動揺の時系列データの相互相関により同期を定量化するにとどまっており、その背後に潜むダイナミクスは検討していない。つまり二者の身体の潜在的な協調ダイナミクスと、顔がそれに与える影響は不明である。そこで本研究は、非線形因果性解析、複雑性解析等の数理解析を用いることで、顔(対面条件、背面条件)が運動協調に与える潜在的な影響を検討する。初年度は、二者の対面、背面の静止立位時の姿勢動揺を計測し、上述した方法論により二者の協調ダイナミクスを定量化する。次年度は初年度で明らかにした二者の協調ダイナミクスが、個人の心理特性や相手への心理状態によって、どのように修飾されうるのかを検討する。本研究により、顔が二者間の運動協調に与える潜在的な影響を定量化する方法論を確立することで、顔が社会相互作用に与える影響や、その発達段階に関する研究や、国際比較研究が可能となり、トランスカルチャー状況下での顔身体学の発展に大きく貢献できる。
研究メンバー
- 工藤 和俊 (東京大学大大学院情報学環・学際情報学府 / 研究協力者)
B01-K105 | 社会的顔認知とその多様性の心理物理学的解析
本吉 勇 (東京大学大学院総合文化研究科)
詳細を見る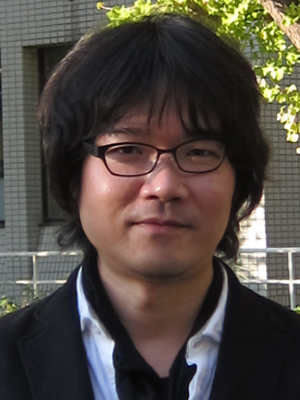
顔認知研究の最も基本的な問題の一つは,観察者が画像に含まれるどのような情報を用い顔の物理的・社会的属性を認識するか,である.本研究計画では,相貌,表情,社会的ステレオタイプなど顔に関する様々な属性の判断において,個々人の観察者が利用する顔画像のなかの情報をより効率的かつ快適に抽出することのできる新たな汎用心理物理学的デコーディング手法群を開発・実装するとともに,それらを駆使して顔認知の個人差・文化差を定量化する新たな研究プラットフォームを構築し,いくつかの重要なテーマについて実証することを目的とする.(1) 顔認知研究では,顔画像をノイズの中に埋め込んだり,ランダムに配置された複数の小さな窓を通して提示した刺激を用い,ノイズや窓の位置と観察者の反応の相関関係を分析することにより,観察者が刺激のなかのどのような情報を利用していたかを数値化する逆相関法がしばしば用いられてきた.しかし,従来の方法には,刺激が明らかに不自然である,莫大な試行数を必要とする,といった問題がある.本研究では,自然な見えをもつ顔画像に対する反応から効率的に観察者の情報利用方略を明らかにする手法を開発し,その有効性を実験により検証する.(2) 顔認知研究では,多くの顔画像について「どれくらい○○か」という心理値を集めることが格別に重要である.そのための古典的方法としてマグニチュード評定が用いられてきたが,社会的ステレオタイプなどの曖昧さをもつ次元で安定したデータを集めるのは困難である.一方,いわゆる一対比較方法は判断が容易で安定した尺度を得ることを可能にするものの,刺激が多くなるにつれ必要な反応数が爆発的に増加するという問題をもつ.そこで,少数の試行に基づき多数の顔刺激に関する任意の心理尺度を効率的に構成する心理物理学的手法を開発し,それを様々な顔認知判断課題に適用する.
B01-K106 | 顔に由来する社会的価値が顔の記憶に与える影響とその神経機構の解明
月浦 崇 (京都大学大学院人間・環境学研究科)
詳細を見る
ヒトの顔には多くの社会的情報が含まれている。そのような顔由来の社会的情報は、ヒトとヒトとの間の社会的相互作用の場面において重要な情報として利用されている。たとえば、初対面の他者が自分にとって魅力的に感じる顔であれば、私たちはその他者に対して好印象をもち、その顔を後々までよく憶えておくことができるかもしれない。しかし、顔に由来する社会的価値が顔の記憶に対して与える影響とその神経基盤については、未だに十分に理解が進んでいない。また、顔に由来する社会的価値は普遍的なものではなく、世代や環境の違いによって影響を受けるため、顔の社会的価値が顔の記憶に与える影響もそれらの違いによって変化することが予測される。本研究では、世代の違いによって影響を受ける顔に由来する社会的価値が、顔の記憶に対してどのような影響を与え、それがどのような脳内機構を基盤としているのかについて、機能的磁気共鳴画像(fMRI)研究から明らかにすることを目的とする。 本研究では、次の2点について研究を進める。第一の研究では、顔の外見的な「魅力」と顔から感じられる他者への「信頼感」に着目し、それらの社会的情報の間の相互作用によって形成される人物の印象が、顔の記憶に与える影響とその神経基盤を明らかにする。また本研究では、健常若年成人と健常高齢者に対して同様の課題を実施し、そこから得られたfMRIデータを群間比較することで、顔の印象が顔の記憶に与える影響の基盤となる脳内機構が、加齢の効果によってどのように変化するのかについても解明する。第二の研究では、顔の新近性判断において顔に由来する社会的情報が与える影響とその脳内機構、およびその加齢変化について、健常若年成人と健常高齢者を対象とするfMRI研究から解明する。これらの研究を通して、顔がもたらす社会的価値が顔の記憶に与える影響とその加齢変化について、その基盤となる脳内機構の全容の理解をめざす。
B01-K107 | 顔・身体認識理解への統合認知進化学的アプローチ:「発達-文化-進化」の観点から
友永 雅己 (京都大学霊長類研究所)
詳細を見る
顔という社会的刺激が発信する情報は多岐にわたるが、現生種間での比較研究を主軸とする比較認知科学では、種や個体に関する情報の認識の研究が圧倒的に多く、性別、年齢、健康状態などそれ以外の重要な情報の知覚・認識については、十分に解明されているとはいいがたい。また、霊長類以外の系統群に目を向けると、種認識や個体認識といった問題でさえ未解決である。さらに、社会的な信号を発信する出力器は顔に限らない。身体そのものもまたわれわれの情報伝達手段として重要な役割を担っている。このことは、ヒトに限ったことではなく霊長類全般に言える。彼らはこのような身体をどのように知覚・認識しているのだろうか。同種の身体と他種の身体の相同性の理解や、成長し変化を続ける身体の一貫性に関する理解に関する研究はまったくの未踏の領域であるといえる。顔および身体は、ともに「全体的処理」を受けることがヒトでは強く示唆されている。本研究計画では、まずこの「信号発信器官」と「全体的処理」という2つの類似性から、顔認識と身体認識の諸相を比較認知科学的に検討し、その相互関係について、系統発生的制約と収斂-多様性の観点から明らかにしていく。この目的を一歩ずつ達成すべく、個別の研究課題を複数設定し、相互に関連づけつつ進めていく。計画している研究課題は以下の通りである。(1)身体知覚における1 次構造/2 次構造の影響の比較認知発達研究、(2)トップダウン的顔知覚の比較認知発達研究、(3)顔・身体認知と年齢認知の関係、(4)イルカおよびウマにおける身体知覚、(5)身体の認識に関する進化-文化-発達、である。これらの課題には比重の多少こそあれ、「進化-文化-発達」という3つの時間軸から認知を考えるという視点が取り込まれている。それぞれの課題について主としてチンパンジーを対象に研究を進めるが、同時にヒトの成人・乳幼児、さらにはイルカやウマなどの哺乳類も対象に研究を進める。
研究メンバー
- 足立 幾磨 (京都大学霊長類研究所 / 研究協力者)
- 林 美里 (京都大学霊長類研究所 / 研究協力者)
- 山本 知里 (京都大学霊長類研究所 / 研究協力者)
- 川口 ゆり (京都大学霊長類研究所 / 研究協力者)
- Jie Gao (京都大学霊長類研究所 / 研究協力者)
B01-K108 | 複数人場面における個人特性と関係性の認知:表情手がかりの効果
上田 祥行 (京都大学こころの未来研究センター)
詳細を見る
円滑な社会生活を送るためには、他者の見た目や行動、喋り方などから、その人物の性格特性や行動の意図を推測し、それに応じた行動をしなければならない。そのため、これまでの多くの研究では、他者と対面する場面において、相手の性格特性の推測に影響を与える要因が検討されてきた。しかし、普段の生活を考えると、私たちが一度にコミュニケーションをとるのは、必ずしも一人の他者とは限らない。例えば、会議・団体スポーツ・集団交流などを考えると、複数人の関係性を理解し、その関係性に応じた振る舞いをしていると考えられる。このような複数人場面における人物の関係性の判断は、「1対1の対面場面で推測された性格特性は、集団の中でも同様に機能している」と考えられていたため、これまであまり検討されてこなかった。本研究代表者らが、実際に対面場面で推測された性格特性が、集団内で同様に機能しているのかを調べたところ、集団内の関係性の判断には集団成員のパーソナリティの推定とは別のメカニズムで行われていることが示された。このような集団内の関係性の判断には、文化の中で共有された無意識的なコミュニケーションの様式・規範が反映されている可能性がある。そこで本研究では、包括的・関係性重視なものの見方が優勢であるとされる東アジア文化圏および分析的・独立性重視なものの見方が優勢であるとされる西洋文化圏において、これらの文化が集団における関係性の判断に与える影響について検討する。西洋文化圏としてアメリカおよびイギリス、東アジア文化圏として日本および台湾において、①集団内の関係性の認知と集団成員のパーソナリティ特性の認知の違いがそれぞれの文化で見られるか、②自己の所属文化圏および非所属文化圏の人物集団においてこれらの認知特性は異なるのか、③これらの認知特性を司る神経基盤の違いについて明らかにする。
研究メンバー
- 吉川 左紀子 (京都大学こころの未来研究センター / 研究協力者)
B01-K109 | 大脳皮質処理と皮質下処理が顔認知に与える影響: 計算モデルと心理実験による検討
稲垣 未来男 (大阪大学 大学院生命機能研究科)
詳細を見る
[研究概要]本研究は大脳皮質経路と皮質下経路が顔の視覚的な認知過程に果たす役割の解明を目標とする。霊長類で高度に発達した大脳皮質経路と進化的に古い皮質下経路は顔認知の異なる側面を担うと考えられるが、その解明には同時に並列的に働く2つの神経経路の影響を切り分ける必要がある。この問題点に対して、大脳皮質経路処理と皮質下経路処理の計算モデルをそれぞれ構築し、それら2つの計算モデルから新規視覚刺激を作成して心理実験を行う研究を提案する。2つの神経経路処理の働きをそれぞれ特異的に強調する人工的な顔画像を使って心理実験を行うことで、それぞれの経路処理が顔認知のどのような側面に貢献しているのかを明らかにする。 神経経路処理の計算モデル構築に当たっては、実際の脳のふるまいに近いモデルとなるように拘束条件を指定する必要がある。私はこれまでに神経活動記録実験を通じて、大脳皮質と皮質下における顔の視覚情報処理の特性を個々の神経細胞レベルで調べてきた。これら神経生理学の実験結果をモデルの拘束条件として用いるとともに、過去の神経解剖学の知見もモデルの拘束条件として利用する。完成した2つの計算モデルを使って、2つの神経経路処理の働きをそれぞれ強調する顔画像を人工的に作成する。神経科学の知見を生かした計算モデル構築と視覚刺激作成に取り組む。 顔の表情認識課題を基本として、さまざまな種類の心理実験(正答率、反応時間、皮膚コンダクタンス反応など)を行い、大脳皮質経路と皮質下経路の2種類の強調顔画像に対する反応を比較する。大脳皮質経路処理と皮質下経路処理が、意識的な反応だけでなく無意識的な反応も含めて顔認知のどのような側面に貢献しているのかを調べる。本研究は計算モデル構築と視覚刺激作成を通じて心理学・認知科学と神経科学の融合的な研究を目指す。
研究メンバー
- 篠崎 隆志 (情報通信研究機構 脳情報通信融合研究センター / 研究協力者)
B01-K110 | 可視的変形の手術後における自己顔の再認知過程
社 浩太郎 (大阪大学大学院歯学研究科)
詳細を見る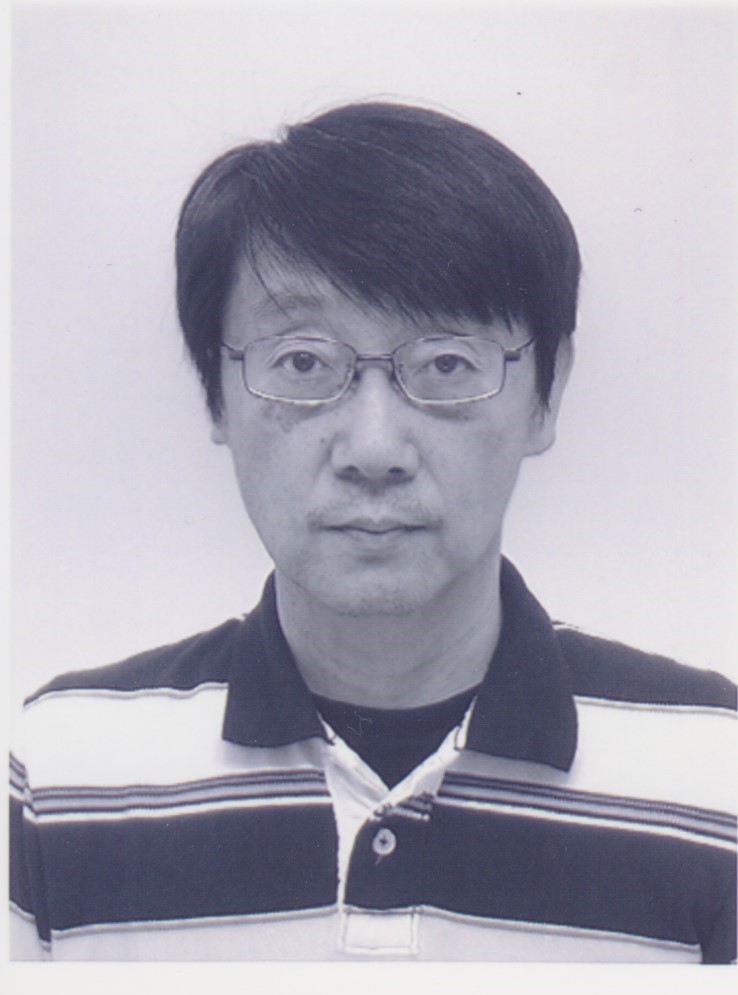
人間にとって、自己の顔は、社会の中で唯一無二の自己を象徴するものであり、表情表出を介して他者とのコミュニケーションを可能にするものである。我々の脳には、他者の顔との対比的な、自己の顔に特有の脳内表象が存在することが知られている。このような自己の脳内表象は、どのように形成されるのであろうか?また、その表象は可塑的で、更新され得るのだろうか?
これらの問いは顔認知の神経科学における未解決の根本問題である。この問いを検証するためには、論理的には、顔を変化させ、新しい顔を再び自分に特有の顔として新しく表象する過程を検証する必要がある。この方法論は、多くの心理学者や神経科学者には、倫理的にも方法論的にも立証不可能に思われる。しかし、顎変形症を有する患者の顔の可視的変形(VD)を外科的矯正治療により、合目的的に治療することによって、この問いの検証が可能となる。研究代表者は、変形した顎顔面の運動スキルは正常以下の値から、手術によりさらに低下して、その後に約2年かけて正常値にまで回復することを示してきた。患者の社会的なQOLも、術後の低下から約1-2年かけて標準以上まで上昇することが示唆されている。
そこで、本研究は、「自己顔の脳内表象は手術の介入で撹乱されて一時的に他者顔の表象へ融合されるが、術後2年間で別の新たな表象へと分化、更新される」という仮説を立て、行動学的手法と神経科学的手法による仮説検証を行う。本研究では、顎骨切除術で急激に変化した新しい顔を、患者はいつ、どのように、どのくらい独自の顔として再認知するかを明らかとする。神経科学的手法(脳機能画像(fMRI))で分かる潜在的な認知の変容過程、心理行動学的手法で分かる顕在的な認知の変容過程及びそれらの関連を検証する。本研究は、外科的矯正治療の診断・治療・ケアーを専門とする臨床研究者と認知・運動神経科学を専門とする研究者との共同研究である。
これらの問いは顔認知の神経科学における未解決の根本問題である。この問いを検証するためには、論理的には、顔を変化させ、新しい顔を再び自分に特有の顔として新しく表象する過程を検証する必要がある。この方法論は、多くの心理学者や神経科学者には、倫理的にも方法論的にも立証不可能に思われる。しかし、顎変形症を有する患者の顔の可視的変形(VD)を外科的矯正治療により、合目的的に治療することによって、この問いの検証が可能となる。研究代表者は、変形した顎顔面の運動スキルは正常以下の値から、手術によりさらに低下して、その後に約2年かけて正常値にまで回復することを示してきた。患者の社会的なQOLも、術後の低下から約1-2年かけて標準以上まで上昇することが示唆されている。
そこで、本研究は、「自己顔の脳内表象は手術の介入で撹乱されて一時的に他者顔の表象へ融合されるが、術後2年間で別の新たな表象へと分化、更新される」という仮説を立て、行動学的手法と神経科学的手法による仮説検証を行う。本研究では、顎骨切除術で急激に変化した新しい顔を、患者はいつ、どのように、どのくらい独自の顔として再認知するかを明らかとする。神経科学的手法(脳機能画像(fMRI))で分かる潜在的な認知の変容過程、心理行動学的手法で分かる顕在的な認知の変容過程及びそれらの関連を検証する。本研究は、外科的矯正治療の診断・治療・ケアーを専門とする臨床研究者と認知・運動神経科学を専門とする研究者との共同研究である。
研究メンバー
- 池上 剛 (国立研究開発法人情報通信研究機構・脳情報通信融合研究センター脳情報通信融合研究室 / 研究協力者)
- Gowrishankar Ganesh (国立研究開発法人産業技術総合研究所・知能システム研究部門 / 研究協力者)
B01-K111 | 個体関係認知の神経基盤とそのトランスカルチャー比較
岡本 正博 (福島県立医科大学医学部)
詳細を見る
社会的認知能力には、対象である個体(人物)を識別し、その個体との関係(血縁、グループ、協力・非協力など)を認知する能力が含まれる。最近の進化心理学の知見からは、社会集団のサイズの急激な増大が、ヒト化(hominization)における大きなステップであったことが示されている。このため、大規模な社会集団における複雑な個体間関係を処理する認知能力がヒトにおいて高度に発達したことが強く示唆される。しかしながら個体間関係の認知に関する神経科学的研究はこれまで殆ど行われていない。最近、機能的磁気イメージング(fMRI)信号に対する巧妙なコーディング・デコーディング技術が発達し、fMRI を用いた、脳内における情報表現の解明が可能になりつつある。本計画ではこのようなfMRI コーディング・デコーディング技術の最近の進歩を、個体間関係の認知に関する神経科学的研究に応用し、以下の二点を明確にする。1. 個体(人物)知識の脳内表現:社会心理学的に、個体(人物)に対する知識は、心理尺度に対する多変量解析の結果、3-5 次元程度の意味空間内に構造化されることが示唆されている。しかしながら、人物に対する知識の脳内表現がどのように構造化されているかについては明確でない。本研究では自然言語処理技術などを用いて人物関連知識の構造を明らかにした上で、fMRIコーディング・デコーディング技術を用いて、人物に関する知識の脳内表現がどのように脳内に表現されているのか、とくに、複数の意味的カテゴリーに基づき構造化されて表現されているのか、を検証する。2. 家族(親族)関係の脳内表現:最も基本的な個体間関係のプロトタイプとして家族(親族)関係がある。文化人類学的に、家族関係は未開社会のコミュニケーションの基礎構造であったことが示されている。しかしながらヒトの家族関係の脳内表現に関する研究はこれまで殆ど行われていない。本研究ではfMRI コーディング・デコーディング技術を用いて、家族関係がどのようにヒトの脳内で構造化され、表現されているのか、を検証する
研究メンバー
- 永福 智志 (福島県立医科大学医学部 / 研究協力者)
- 藤原 寿理 (福島県立医科大学医学部 / 研究協力者)
B01-K112 | 顔面表情認知にしぐさ・姿勢が及ぼす影響に関する実験的検討
渡邊 伸行 (金沢工業大学情報フロンティア学部)
詳細を見る
他者の顔から「喜んでいる」、「怒っている」というような情動を読み取る顔面表情認知において、しぐさや姿勢がどのような影響を及ぼすか、検討することを目的とする。表情認知に関するこれまでの心理学研究において、「快―不快」、「活動性」という感情的意味次元に基づく判断が行われていることが、繰り返し確認されてきた。また、表情認知に影響を及ぼす顔以外の文脈情報 (顔以外の非言語情報、表情が表出された状況、表出者と観察者の関係性、および文化差など) は、上記の感情的意味次元に基づく判断の段階で影響を及ぼすと言われている。本研究では文脈情報の一つであるしぐさ、姿勢に着目し、表情と組み合わせた場合に、表情認知にどのような影響を及ぼすか、検討する。 実験では、表情としぐさ、姿勢を組み合わせた画像を刺激として呈示し、実験参加者に表情の意味評価や、感情カテゴリー判断を求める。表情は基本表情 (喜び、驚き、恐れ、悲しみ、怒り、嫌悪、軽蔑) の典型表情や、より自然な状況で表出される表情などを用いる。しぐさや姿勢については、Posture Scoring SystemやBody Movement Scoring Systemなどの非言語行動分類システムに基づいて選出する。モデルに表情としぐさ、姿勢を組み合わせた演技を求め、それを撮影して刺激画像とする。撮影した刺激は、Facial Action Coding System (FACS) や上記の非言語行動分類システムに基づいた分析を行い、刺激の妥当性を確認する。実験ではセマンティック・ディファレンシャル法に基づいた評価や、感情カテゴリー判断などを実施する。分析によって、しぐさや姿勢が表情認知にどのような影響を及ぼすかを明らかにしたい。また、可能であれば比較文化研究を実施して、しぐさや姿勢の影響の文化差などについても明らかにしていきたい。
B01-K113 | 他者心理の手がかりとしての表情理解に関する哲学的・認知科学的研究
長滝 祥司 (中京大学 国際教養学部)
詳細を見る
現象学が身体性や志向性などの概念を使って明らかにしてきたように、人間の日常経験は、意識されない知覚や行動が多くを占めている。同時に、われわれが他者の行動や心的状態を理解する際にも、多くの場合無意識に、表情や身体動作を読み取ったり、それらをもとに他者に一定の心的性質や道徳的性質を帰属させたりしている。本研究では、現象学や心の哲学を理論的背景として、心理学や脳科学の実証的方法によって得られたデータを用いながら、人間が無意識に行なっているそうした作業に基づく他者理解のメカニズムを解明することをめざす。このメカニズムを解明するために、(ア)現象学や心の哲学を中心とする哲学的な理論と、心理学や脳科学のような自然科学とを適切に融合するための新たな方法論を作ること、(イ)心理学的、脳科学的な実験を遂行し、そこで得られたデータを(ア)で構築した方法論にもとづいて分析し、(ウ)この分析にもとづいて(ア)の方法論を反省的に洗練させていくこと、の三つを行う。 具体的な実験手法については割愛するが、われわれは、上記の実験によって人が他者の心的状態や特性を理解する際に何を手がかりにしているかを解明するためのデータを三つ得ることになる((A) 他者の作業映像を観察して、その人の心的特性等を理解するときどこに注目したかを被験者が具体的に記述したデータ、(B) この具体的記述データを質的研究ソフトNvivoVer.11によって解析したデータ、(C) 作業映像を観察している際の被験者の脳データ[EEGデータ・EOGデータ・Muリズムデータ])。これらのデータをどのように関連づけるかが、先のメカニズムの解明にとって重要な鍵となる。以上の試みによって、他者理解をめぐる日常経験に関して、その自然化可能性の射程と限界が明らかになることが予想される。
研究メンバー
- 山田 純栄 (京都大学大学院医学研究科 人間健康科学 / 研究協力者)
B01-K114 | 他者の視線が自己の行動に与える影響の文化差:二者同時記録fMRIを用いた検討
小池 耕彦 (生理学研究所 システム脳科学研究領域)
詳細を見る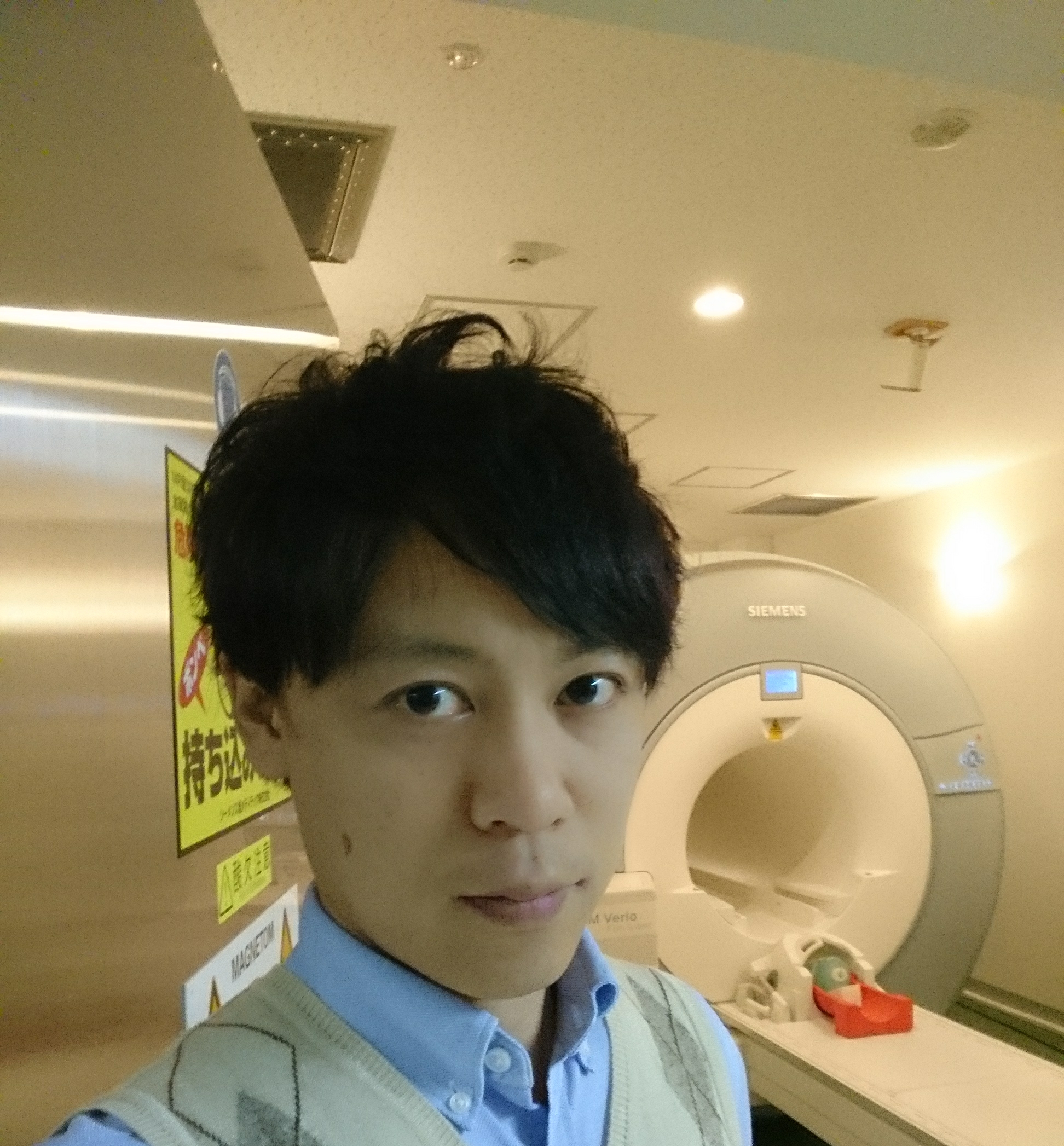
視線を介した非言語コミュニケーション(みつめあい,共同注意など)は,ヒトの発達段階の初期に獲得される社会能力であり,他の能力の基盤となっている.視線コミュニケーションは出力(行動)と入力(知覚)が眼球という同一の組織で担われていることから,その理解においては二者間での再帰的な情報交換という側面を無視することはできない.私はその神経基盤を,二者同時記録可能な機能的磁気共鳴画像法(fMRI)を用いて検討してきた.その結果,視線コミュニケーション中にヒトは,視線や瞬きの情報を他者のそれに随伴させること,それに伴い右下前頭回の脳活動相関が観察されることを示した.自他の行動を無意識的に随伴する作用は,個人脳内では知覚-運動連合によって担われており,これが他者の視線を自分の行動に組み込み,二者を一つに繋ぐメカニズムの基盤と考えられる.自他の視線を随伴させる行動は,一緒に物を探す場合などに見られる,一般的な社会行動である.しかしその行動の文化差については,全く明らかになっていない.先行研究によれば,日本人はフィンランド人と比較して,視線が向けられた顔画像を『近づきがたい』と評価する.このことは他者の視線を自分の行動に反映するメカニズムおよびその神経基盤にも,文化差がある可能性を示唆する.本研究では,以下の目標を設定して,社会的場面で自他の視線を随伴させる行動およびその神経基盤について,文化特異性および汎文化性を解明する.目的1:コミュニケーション場面において他者の視線情報を利用する傾向の文化差および共通性を検討する.他者の視線情報をリアルタイムで利用可能な視覚探索課題を用いる.目的2:他者の視線利用について異なる方略をとる異文化間でコミュニケーションをおこなった際に,発生する現象を解明する.目的3:他者の視線情報を利用して自分の行動に活かす際の脳活動を二者同時記録MRIにより記録し,文化を超えた共通性および文化差について検討をおこなう.
研究メンバー
- 笠井 千勢 (岐阜大学 地域科学部 / 研究協力者)
B01-K115 | 深層学習による顔・身体画像表現の異文化差の解明
林 隆介 (産業技術総合研究所 人間情報研究部門 システム脳科学研究グループ)
詳細を見る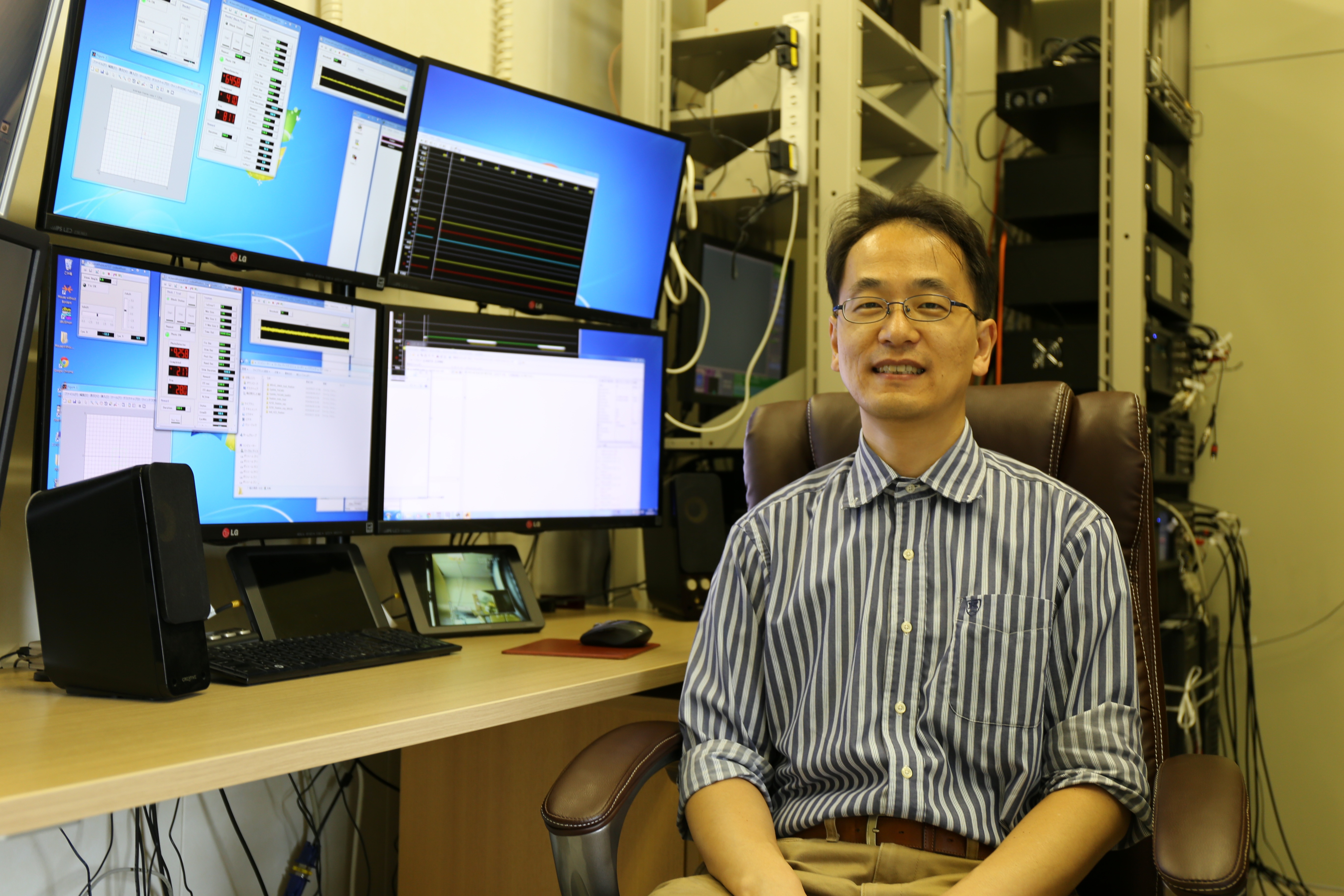
顔と身体表現の異文化を作りあげるメカニズムの一つとして、各コミュニティー内での発達過程における視覚体験の違いがあげられる。視覚体験の違いが、脳内情報表現にどのような違いを引き起こすのか情報工学的に解明することは、赤ちゃんを用いた発達研究や異文化間の比較心理学的研究とならんで、顔・身体学の構築に不可欠な研究アプローチである。視覚情報処理装置としての脳は、階層的な畳み込み演算により、さまざまな入力画像を復号化可能な形で圧縮表現する符号化装置ととらえることができる。こうした情報処理は、深層ニューラルネットを利用した機械学習法によって実装可能となりつつある。
本研究では、人間の脳が視覚情報処理を学習する際の学習原理として、各ニューロン活動の情報量最大化やスパース性といった拘束条件を仮定し、大規模な顔・身体画像データを学習した深層ニューラルネットワークが、どのような顔・身体情報表現を自己組織的に獲得するのか明らかにすることを目標とする。そして、当該新学術領域内のフィールドワークを行うグループから、さまざまな文化圏で収集された画像データを提供いただき、深層ニューラルネットを文化圏別に学習させ、個々の深層ニューラルネットが獲得する画像特徴量や画像統計量を比較検討することで、顔と身体表現の文化差を生み出す基礎的メカニズムの情報工学的解明をめざす。
本研究では、人間の脳が視覚情報処理を学習する際の学習原理として、各ニューロン活動の情報量最大化やスパース性といった拘束条件を仮定し、大規模な顔・身体画像データを学習した深層ニューラルネットワークが、どのような顔・身体情報表現を自己組織的に獲得するのか明らかにすることを目標とする。そして、当該新学術領域内のフィールドワークを行うグループから、さまざまな文化圏で収集された画像データを提供いただき、深層ニューラルネットを文化圏別に学習させ、個々の深層ニューラルネットが獲得する画像特徴量や画像統計量を比較検討することで、顔と身体表現の文化差を生み出す基礎的メカニズムの情報工学的解明をめざす。
C01-K101 | 日本、中世の絵巻物にみる人物表現の顔と身体の表情に関する研究
宮永 美知代 (東京藝術大学大学院美術教育(美術解剖学II)研究室)
詳細を見る
日本人の顔の表情や身体表情は、性、年齢、当時の社会的身分、また時代こ゛とにと゛のように異なったのか。写真以前の顔や身体表情等については、専ら文献から意味内容か゛解釈されてきた。一方て゛絵画等の造形作品の人物表現をもとに、描かれた個々の顔を具体的な表情や動作を有する人の姿として、解剖学的構造との関係て゛論し゛、あるいは描かれた人物の顔と身体の表情や仕草についての調査はほとんと゛行われてこなかった。 本研究では、日本の鎌倉時代の絵巻に見られる多様な人物表現の顔と身体の表情について、個々の顔面器官の形と配置等の顔の特徴と構造との対照、およひ゛表情をつくる各機関の形を類型別化等の分析をし、表情についての顔の特性から、統計的・実証的手法をも採り入れ、表情の描写の特性、及ひ゛、描かれた中世の人々の顔と身体の表情特性について、多様な切り口から重層的に顔と身体の表情の特徴を明らかにしていく。
研究メンバー
- 前田 基成 (女子美術大学美術研究科美術教育 / 研究協力者)
C01-K102 | 身振り概念の変化のメカニズムに関する美術史的考察―古代ギリシア・ローマ美術から
田中 咲子 (新潟大学 教育学部 芸術環境講座)
詳細を見る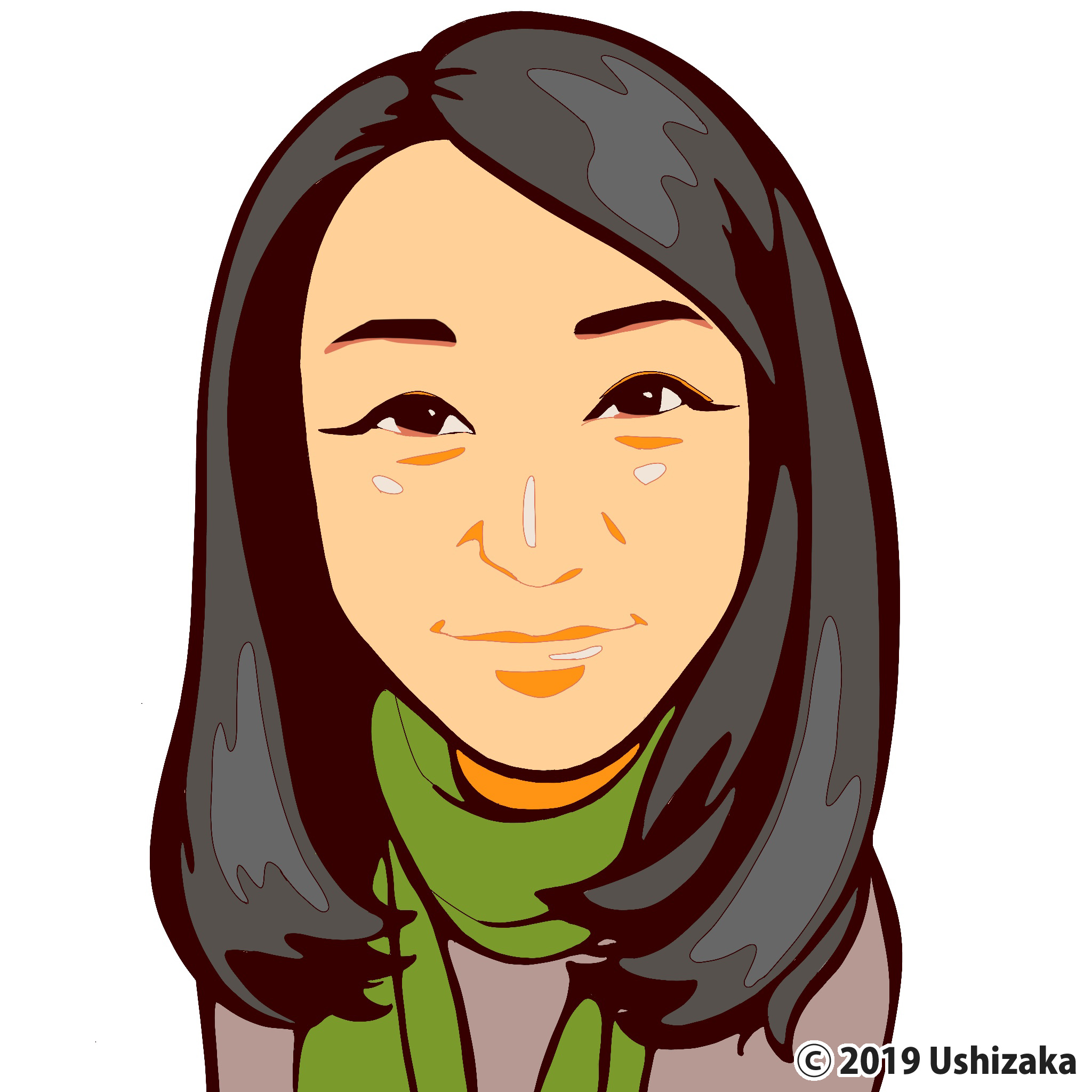
本研究は、美術作品に見られる身振り表現を研究対象とする。とりわけ、古代ギリシア・ローマ美術における「両手を前方に上げる、かざす」身振りに着目する。当該文化圏の造形表現において、この身振りは祈祷、哀悼、嘆願、そしてキリスト教の祈り等、様々な意味を付与されてきた。そこで本研究では、古代ギリシア・ローマという同一もしくは近似する文化圏において、同一の身振りの意味や形態が変化するメカニズムを、美術史学や古典考古学を主たる方法論とし、歴史的、社会的観点を加味して解明することを目指す。 古代ギリシア・ローマ時代は、狭義においても紀元前10世紀頃から紀元後5世紀に至る約1500年という長期間に及ぶが、その間、文化は、巨視的に見れば直接的な継承が続いてきたといってよい。例えば、絵画や彫刻といった造形表現においては、人物像の身振りが言語として機能して文字に代わる意味伝達の役割りを担ったわけであるが、その多くは時代を超えて継承された。しかし他方、同一の身振りが時代や文脈において異なる意味を付与されることもあった。また、特定の身振りが性差や民族の違いを特徴付け、価値観を表出することもあった。本班の予備的調査では、「両手を前方にかざす」身振りがそうした例に該当し、時代順に祈祷、哀悼、(臆病者による)嘆願、哀悼と嘆願の並存、そしてキリスト教の祈り、という大まかな変遷の図式を描くことができるとの仮説を得ている。本研究では、こうした変遷過程を詳細にわたって再検討した上で、かかる意味の変化や、ときには表象形態の変化を引き起こした要因を社会背景の中に求め、その具体的事例を明らかにする。造形芸術における身振り表現は、現実をそのまま反映することもあれば、何かしらのバイアスがかかる場合もある。本研究では、資料が限られる古代ではあるが、現実と表象との齟齬についても可能な限り明らかにしたい。
研究メンバー
- 小堀 馨子 (帝京科学大学 総合教育センター / 研究協力者)
- 坂田 道生 (千葉商科大学 / 研究協力者)