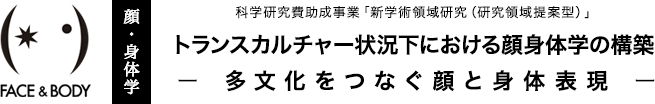計画班A01-P01
「顔と身体表現の文化フィールドワーク研究」
研究の概要と目的
現在、インターネットなど電子メディアの発達によって、文化や情報の地域や国境を越えた流動や混淆(いわゆるトランスカルチャー的状況)が顕著となっている。この状況は、私たちの顔や身体をめぐる経験にも大きな影響を及ぼしている。例えば、私たちは今や電子メディア等を通じて、これまでの社会にみられることのない規模で、あらゆる/たくさんの顔(や身体)のイメージにさらされるようになっている。その結果として、顔(や身体)に関する解釈や価値づけ、美意識等に関するグローバルな規模での標準化・画一化の圧力に晒されている。にもかかわらず、他方ではイスラーム圏におけるヴェールによる顔の隠蔽やバリ島における仮面芸能の持続などに代表されるように、ローカルな文化や個別の文脈ごとの顔や身体に関する独自の意味づけや実践なども逆に重要性を増しつつあるようにも見える。本研究では、以上のような状況認識を前提としながら、フィールドワークを含む文化人類学の手法を駆使することで、イスラーム圏やヒンドゥー文化圏等を含むアジア域内の異なる文化圏や地域の実際の生活現場における顔や身体的表現や実践をめぐる差異(と共通性)に関して具体的に比較検討することを目的としている。
手法と対象
本研究班は、人類学的フィールドワークを含むフィールドサイエンスの研究手法を駆使し、顔と身体表現について、現場の文脈に即した調査研究を行う。顔や関係する身体表現に関して、イスラーム圏を含むアジア(東・東南アジア)域内における異なる文化・社会的文脈に応じた比較研究を遂行する。狭義の顔はもちろん、顔を含む各種の身体的表現、衣服、装飾、仮面、ヴェール・スカーフ、あるいはフェイスブックをはじめとするインターネットを含むメディア上の顔や身体に関わる表象・表現などに関して調査研究を実施し、地域や文化ごとの差異と共通性を析出する。
関連出版物
- 床呂郁哉(編)2017『トランスカルチャー状況下における顔・身体学の構築(シンポジウム報告書)』
東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所 - 床呂郁哉(編)2016『顔と身体表現に基づく異文化理解(シンポジウム報告書)』
東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所
メンバー構成
- 研究代表者:床呂郁哉(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所・教授)
- 分担研究者:西井凉子(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所・教授)
- 分担研究者:吉田ゆか子(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所・准教授)
- 分担研究者:塩谷もも(島根県立大学人間文化学部・准教授)
- 分担研究者:田中みわ子(東日本国際大学健康福祉学部・教授)
- 研究協力者:吉田優貴(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所・研究機関研究員)
- 研究協力者:後藤真実(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所・日本学術振興会特別研究員PD)(2019/04〜)
- 研究協力者:池田昭光(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所・研究機関研究員)(〜2019/03)
(※なお研究の実施に当たっては東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所(AA研)の基幹研究人類学班ならびに、AA研の海外拠点の一つであるコタキナバル・リエゾンオフィス(KKLO)などとも協力しながら、各種の研究活動やアウトリーチ活動等の企画を実施していくことを予定している。)